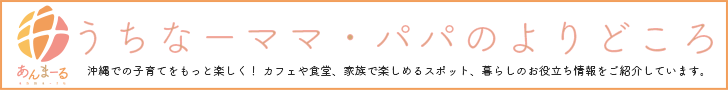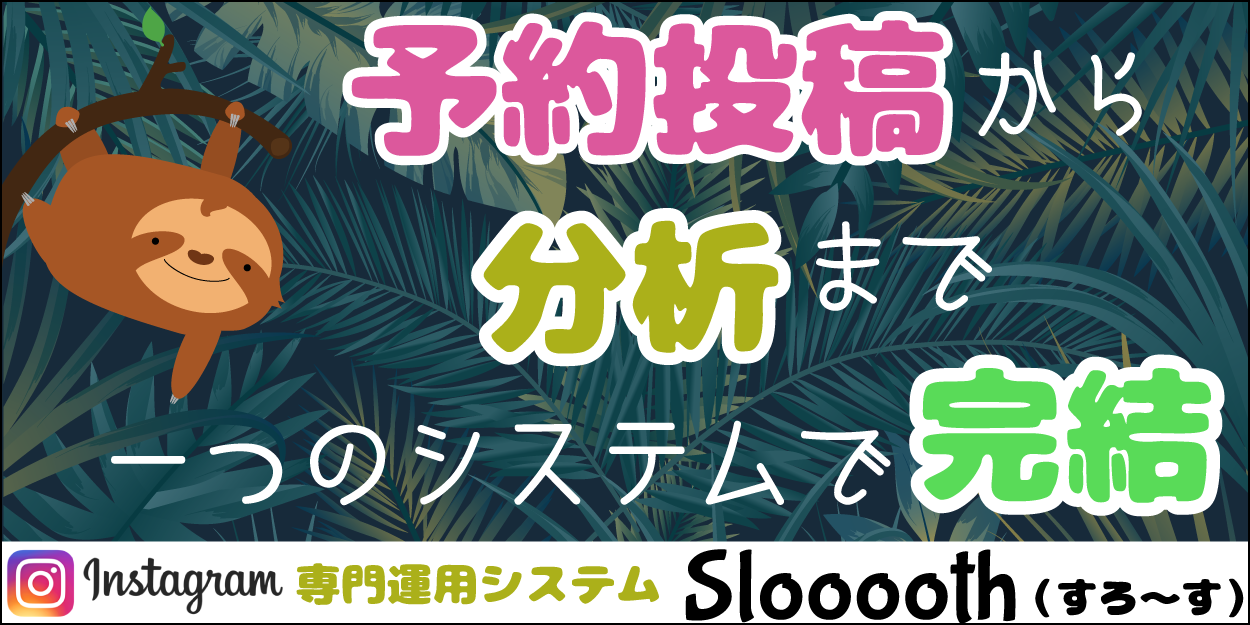修正指示がきた!そのまま直して返していませんか?【記事・写真・デザイン】
こんにちは、よしてるです。
余談ですが、NICO Touches the Wallsというバンドの『天地ガエシ』という曲の歌詞が大好きです。歌詞をそのまま書くことはできないのですが、ラストサビの内容が「どんなに一生懸命にやっても『いったい何が変わったのか』って吐き捨てられたよな?」と訴えかけるもので、頑張っても報われない日々に言葉を添えてくれてすごく励まされるのです。
さて、クリエイティブな仕事においてはクライアントや上司から修正指示をもらうことが多々あるかと思いますが、もし言われたとおりに直して返しているだけだとほぼ間違いなく「いったい何が変わったのか」と思われています。
記事作成:「この表現をこれに変えてください」
写真:「少しだけ寄り目にトリミングしてください」
デザイン:「ここは不要なので消してください」
修正指示に対しては、できる限り、プラスアルファで返すようにすることが重要です。
目次
なぜ修正をそのまま返してはいけないのか?
言われたままに返した修正でOKをもらったとしても、「いったい何が変わったのか」と思われたままです。その案件は問題なく終わるかもしれませんが、次もあたなに仕事を振りたいと思うか、ここに影響してきます。
では、なぜそのまま返してはいけないのでしょうか。
本当に何も直っていないように見える
これはチェックする人特有の感覚なんじゃないかと思いますが、こちらが「こう直してください」と言ったものが本当にそのまま返ってきたとき、「いったい何が変わったのか」と感じるのです。
直す側としては「言われたとおりやったじゃないか」と思うかもしれません。しかしこれは理屈ではなく感覚なので、仕方がないのです。NICO Touches the Wallsの『天地ガエシ』の歌詞が大好きな私も、いざチェック側になると吐き捨てる側に回ってしまいます。
なお、本当にそう直すしかないものはさすがに除きます。記事作成における単なる誤字とか、デザインにおける数字の修正とかですね。
記事作成:「この表現をこれに変えてください」
写真:「少しだけ寄り目にトリミングしてください」
デザイン:「ここは不要なので消してください」
このくらいのレベルから、プラスアルファの修正が欲しくなります。とはいえ、修正を渡すほうも「プラスアルファの修正が欲しい」と思いながら渡しているわけではなく、渡すときはそのとおりで返ってくることを想定しています。それなのにいざそのまま返ってきたら「いったい何が変わったのか」と思ってしまうのだから、修正を渡すほうも複雑です。
そのまま直すだけなら修正させる意味がない
私は、クライアント側か社内かでいえば社内で修正を渡すことが多いのですが、社内だと特に「いったい何が変わったのか」という感覚が強いと思います。なぜなら、そのまま返ってくるだけなら自分で直して出したほうが早いからです。
なお、社内であればそのままの修正も本当に無意味というわけではありません。自分の手で直させることは作成者にとってもスキルを伸ばす機会になるからです。
ただ、社内だとそれ以上の成長を期待したいところがあります。自分で「これはどう直すのがベストなのだろう?」と考えて直してくれたほうが、仮にその修正が外れていたとしても成長につながります。
クライアントの本当のニーズを汲み取れない可能性がある
クライアントからの修正の場合、また別の問題として「本当のニーズを汲み取れない」が発生します。
クライアントは、記事作成、写真、デザイン、その他クリエイティブな作業に関して基本的には素人です。ときには、素人視点での修正を渡してしまうことがあり、明らかに「それは違うんだけどな」と思うこともあります。
「それは違うんだけどな」というレベルでなくても、社内の修正と比べて、クリティカルな修正指示を出せる可能性はどうしても低くなります。クリティカルな修正というのは、その成果物を用いて何を達成したいかという課題に近づける修正です。クライアントはそのスキル(あるいは時間的リソース)がないために専門業者へ依頼しているので、ここは私たちでコントロールしてあげる必要があります。
そのため、クライアントからの修正をそのまま返してしまうと、その場は問題なく進んでも、結果的に目的の達成からは遠ざかります。また、私たちの課題解決能力も上がっていかないので、今後の仕事に影響するかもしれません。
具体的にどんなプラスアルファが必要?
言ったとおりに直しても不十分ならどうすればいいのか、というところで、具体的な考え方について見ていきましょう。以下は「こうすればOK!」と一概には言えないものですが、私が作成者側として実践してきたものです。
記事作成:よりよい表現を探す
記事作成:「この表現をこれに変えてください」
当然、指定された表現に直すだけでは不十分です。特にクライアントからの修正であれば、クライアントは文章の前後の関係まで見ることはできないので、的外れな修正指示になっていることもあります。もちろん、社内修正でもただ直すだけでなく、その前後まで確認し、よりよい表現を探します。
なお、修正のフェーズが発生するということは、成果物をブラッシュアップするチャンスでもあります。クリエイティブな仕事において、100%を最初から出すことは不可能です。修正指示の周辺も見直し、よいよい記事を納品できれば花丸でしょう。
写真:見た目を大きく変える
写真:「少しだけ寄り目にトリミングしてください」
写真の場合、「少しだけ」直しただけでは本当に何も直っていないように見えます。これは本記事における「いったい何が変わったのか」ではなく、写真だとわざわざ並べて見比べない限り変化がわからないという意味です。なので、写真に対する修正では指示よりも大きく直す必要があります。
トリミング指示であればけっこうトリミングしますし、明るさ指示であればけっこう明るくします。それも過ぎてしまうと変な写真になってしまうので、難しいですが、ここはカメラマンの腕の見せ所です。
デザイン:バランス含め細かく調整する
デザイン:「ここは不要なので消してください」
さすがにデザインにおいて、不要なものを消したあとに何も調整しないことはないと思いますが、それでもその周辺も含めて細かい調整を行います。
クライアントからのデザインの修正においては、具体的な指示というよりは「ここをこんなふうにしたいのですが…」という曖昧な相談ベースもよくあります。こういった修正に対しては、クライアントの言葉の裏にある課題を読み取り、クリティカルな修正を探す必要があります。
丁寧な仕事は気持ちがいい
最初から100%のクリエイティブを提出できたり、一度の修正指示に対してクリティカルな修正を返したりできれば理想です。ただ、文章も写真もデザインも、クリエイティブな仕事でミスを完全に消すことはできないですし、クオリティが足りずに結果が伴わないこともあるでしょう。
それでも、丁寧に仕事をしてくれる人とは仕事をしていて気持ちがいいものもです。修正指示に対してプラスアルファで返すことは、気持ちのいい仕事に大きく近づきます。「いったい何が変わったのか」と思われることも、かなり少なくなるでしょう。