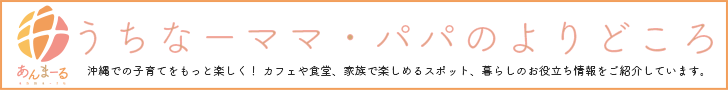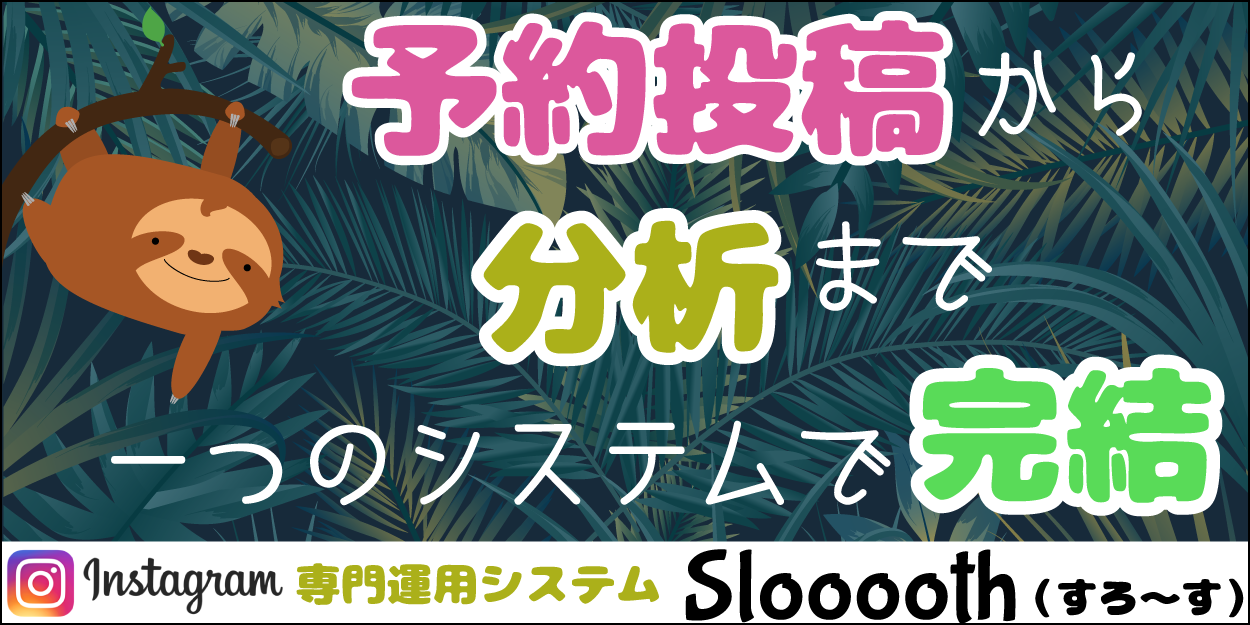どうしてミスが起きてしまうのか?考えられる原因と解決策について
できるだけミスをしないように気をつけていても、なぜかミスをしてしまうことってありますよね。
こんにちは。LOVELETTER WORKS株式会社の長浜です。
「最近ミスが多いな……」と感じたので、今回は最近ミスしたことやミスをしてしまう原因・対策を考えてまとめていきます。
目次
最近ミスしたこと
最近ミスしたことは、記事の確認不足です。
専門的な案件で、先方から細かくレギュレーションが指示されており、記事作成をしたあとはレギュレーションシート+自社で使用している確認シートを見ながらチェックしていました。ですが、先方から「レギュレーションを確認している方はいるのか」とのご質問が。
直接「レギュレーションミスがある」と言われたわけではありませんが、その質問が来るということはミスしていることだと思うので、「確認により気をつけていかなければいけないな」と思いました。
ミスしてしまいがちな原因とは?
わたしがミスをしてしまったとき、「これが原因だろうな」と思うものは主に以下の3つです。
焦ってしまう
特に多いのが「焦り」です。
わたしは普段、記事案や記事を作成したら最低でも2日は寝かせておき、翌日以降に再度確認をするようにしています。そうすることで頭を一旦リセットでき、客観的に見れるようになるからです。書いたときは「これが正しい」と思ってしまいますが、あとから読み返すと「あ、ここは修正したほうが良いな」と気づきやすくなります。
ですが、焦っているとどうでしょう。冷静な判断ができなくなるため、「正しい」と思ってしまうのです。
特に最近は業務が立て込んでいることもあり、記事が完成するのが納品日の前日ということもしばしば。作成時にもチェックはしているので、時間がないと「大丈夫」と思って納品日当日は1文字ずつ細かくチェックせず、さーっと目を通すだけのときもあります。これにより、ミスに気づかないまま先方に提出し、修正がきてしまうのです。
信用してしまう
次に多いのがチェック時に「相手(作成者)を信用してしまうこと」です。
信用するのがいけないわけではないのですが、人間誰しもミスはするものです。相手が絶対にミスをしないということはほとんどありません。そのため、本来であれば疑って確認をする必要があると思うんです。
ただ、上司や先輩など経験・立場が上の人が相手となるとどこかで信じ切ってしまうことはあるかと思います。
わたしの場合、「しっかり確認しておけば良かった……」と思ったのがクライアントです。Instagram広告のクリエイティブをクライアント側で作成していただいているとき、共有されたタイミングで誤字・脱字がないかは確認していました。ただ、それ以外の箇所に関しては「これまで問題なかったし大丈夫」と思って確認をしていなかったのです。
その結果、広告を配信したあとにクライアントから「CTAボタンと文字が被っている」とご指摘があったのです。正直、この連絡がきたときは『うわ、やってしまった……』とすごく凹みました。
配信をする前にプレビューでしっかり確認をしておけば、配信後に気づくというミスは防げたはず。
クライアントに提出する前に気づけたので良かったのですが、先日、外注さんに依頼している記事の文字数不足がありました。何度も依頼していた案件で、これまで文字数不足はありませんでした。そのため、外注さんから「完成しました」と連絡をもらったとき、すぐに確認せずにいたんです。
一通りチェックしたあと「文字数少なくない?」と気付き、確認してみたら1,000文字ほど足りず。トータル2記事依頼していたので、もう1記事は文章をチェックする前に文字数を確認。すると、もう1記事は500文字ほど不足していました。
外注さんに加筆してもらい、どうにか納品日に提出することはできましたが、「これまで大丈夫だったから今回も大丈夫だろう」と思っていたせいで確認が遅くなりました。
今までノーミスだった人でもミスをすることはあるので、信用しすぎないことも大事だと感じました。
脳が錯覚を起こしている
頻繁にではないのですが、ミスしてしまう原因のひとつに「脳が錯覚を起こしている」ということもあります。たとえば以下の文章。
『みなさんこんにちは。最近は暑い日が続いていますが、体調は崩していないでしょうか?わしたはしっかりと水分を摂って体調に気をつけています』
文字の順番が入れ替わっているのに、気づかずスムーズに読めてしまうことってありますよね。これを「タイポグリセミア」と言うそうです。
文字の最初と最後が合っていると自然と読めてしまうので、稀にこれに気づかずミスをしてしまうことがあります。
ミスを防ぐための対策
ミスを防ぐためには、「余裕のあるスケジュールを組む」「ミスした内容はメモにまとめる」「指差し確認をする」「ツールを使用する」「チェック体制を強化する」「気持ちを切り替える」の6つが大切だと思います。
余裕のあるスケジュールを組む
わたしがミスをしてしまうのは、大体が焦っているときです。やることが多いと、「次はあれをしてこれをして」と考えながら対応してしまうため、何かしらが抜けてしまうことがあります。たとえば、上司のメールアドレスをCCに入れずに送ってしまうなど。何度やったことでしょう。
余裕があればひとつの業務に向き合うことができるので、ミスを減らせると思います。
ミスした内容はメモにまとめる
「次から気をつけよう」だけで終わってしまうと繰り返してしまう可能性が高いので、わたしはミスした内容はパソコンのメモ帳にまとめるようにしています。
上司のメールアドレスをCCに入れ忘れてメールを送信する件もそうなのですが、ほかにもフォルダの共有設定を変更しないままクライアントにドキュメントを送信し、「開けないので権限をください」と言われたこともあります。
上記のミスを防ぐため、メモ帳には以下を記載しています。
■メールアドレス
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
■CCに入れる
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
■フォルダを共有する
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
〜〜〜〜〜@◯◯◯.co.jp
メールを送る際はメモ帳からアドレスをコピーしているので、「フォルダを共有する」という文字を見ればハッと気づくことができます。これで最近は共有忘れを防げています。
指差し確認をする
すべて指差し確認をしているわけではないのですが、特に気をつけなくてはいけないものに関しては指差し確認をするようにしています。わたしが必ず指差し確認をしているのが「人の名前」です。
個人的に、メールの文章内に誤字・脱字があったとしても伝われば問題ないと思うんです。あまりよろしくはないですが。
ただ、名前を間違えるのは失礼にあたりますよね。メール本文の誤字・脱字よりも名前を間違えられることのほうが良い気がしないと思うので、そこだけは2〜3回指差し確認をしています。
ツールを使用する
弊社では、レギュレーションを確認できるエクセルシートを使用しています。たとえば「◯ヶ月」ではなく「◯か月」表記の場合、「ヶ月」の文字を登録しておくと該当箇所が一目でわかるようになっています。これにより、レギュレーションミスを防ぐようにしています。
誤字・脱字に関しては、上司から「ChatGPTを使えば?」とご提案いただきました。試しにあえて脱字がある文章を貼り付けて「誤字・脱字がないかチェックして」と入力してみたところ、該当箇所をChatGPTが教えてくれました。
ツールも万能ではないと思うので目視チェックは必須ですが、目視チェックしたあとに最終確認としてツールを使用するのは良さそうです!
チェック体制を強化する
弊社では、基本的に自身が担当している案件は自身で最終確認して先方に提出するフローになっています。そのため、チェック者は1人です。
しっかり確認していてもレギュレーションミスや誤字・脱字が発生することがあるので、冒頭で記述した専門的な案件に関しては、ダブルチェック体制に変更しました。
その結果、先方に提出する前に見逃しがあった箇所に気付いて修正することができました。また、「意味は同じだけどこっちの単語のほうが適切ではないか?」という箇所に関しては、チェック者同士で確認してお互いの認識を合わせることができました。
レギュレーションがかなり細かい案件に関してはチェック体制を強化することでミスを防ぎやすくなりますし、案件担当者は精神的な負担が軽減されるので有効だと思います。
気持ちを切り替える
ミスをしたときはほとんどの人が凹むと思うんです。実際にわたしもめちゃくちゃ凹みます。胃が痛くなるほど。
ただ、ミスしたときの気分を引きずっていると仕事のパフォーマンスは上がらないし、さらにミスを引き起こしてしまうと思っています。なので、なるべく早く気持ちを切り替えられるようにしています。
わたしがやっている方法は「業務終了後に違うことに集中する」「その日はなるべく早く寝る」です。漫画を読んだり動画を見たりしている間はそこに集中するので、気分が落ちてしまうのを防げます。これで翌日には気持ちを切り替えた状態で仕事に臨むようにしています。
ミスは学びにつなげよう
わたしは悲観的なタイプなので、ミスをすると「自分はダメだ……」とかなり凹みます。記事のレギュレーションミスや誤字・脱字はもちろんあってはいけないことですが、クライアントからするとミスに感じないほどの些細なミスに関しては、「失敗は成功のもと」「何事も経験」と前向きに捉えるようにしています。
あと、わたしが個人的にミスだと思って凹んでいるとき、関連会社の社長から「何がミスだと思うの?」と聞かれ、話しをして言われたことがあります。それは「ミスを怖がって何もしないことが1番良くない。お客さまのためを思って起こったミスならこっちが謝罪するし怖がらなくて良い」です。
ミスを怖がっているとどうしても動けなくなってしまいがちですが、SNS関連や広告などの業務に関しては恐れずにどんどん挑戦していきたいと思います。