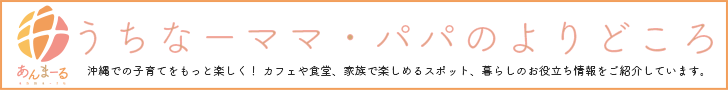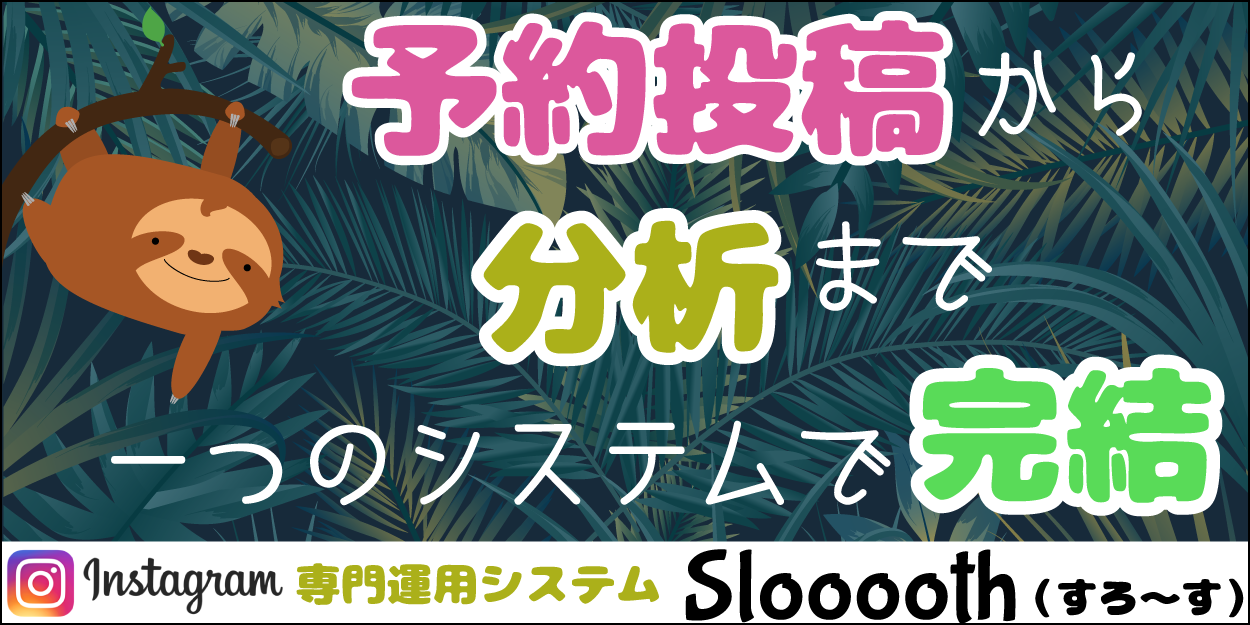読みやすい記事にする5つの条件!重要なのは記事を育てること
こんにちは。LOVELETTER WORKS株式会社 垣花です。
前回は、「検索エンジンが評価するユーザーニーズを満たすコンテンツ」についてご紹介しました。
Googleなどの検索エンジンに評価してもらうためには、ユーザーニーズを満たす良質なコンテンツを作成する必要があるということです。
しかし、サイト運営をする上で「ユーザーにどんな情報をなぜ届けたいのか」ということを考えると、検索エンジンに評価してもらう対策だけをするのはやはり違うと思います。
検索エンジン対策の記事=ユーザーが読みやすい記事 ではないので、検索エンジン対策( SEO対策)をしつつ、読みやすく・わかりやすい記事を作成してしていく必要があると思うんです。
そこで今回は、記事作成の基本とも言える「読みやすい記事とは」について考えていきたいと思います。
目次
読みやすい記事の条件とは
これまで、たくさんのクライアント記事や自社メディアの記事を書いてはチェックしてもらい、たくさんのフィードバックを受けて改善してきました。
そのなかで、学んだことを「読みやすい記事の条件」としてご紹介します。
1. 情報が整理されているか
読みやすい記事は、基本的に情報が整理されています。
そもそも情報の整理とは、Aについて説明する場所にはAについてのみ記載し、Bについて説明する場所にはBについてのみ記載するなど、情報が混在していない状態です。
情報が整理されていない場合、Aの説明とBの情報が混在して読みづらくなってしまいます。
このほか、見出しがなくツラツラとただ文章だけが書き連ねられた記事は、どこに何が書いてあるのかがわからないため読みづらいですよね。見出しがないと欲しい情報がどこにあるのか探すことができないので、きっと多くの人が「読むのを辞めよう」と感じると思います。
そこで重要となるのが情報の整理。
見出しを細かく設定して、必要とする情報がどこにあるのかを明確にすることで、多くの人が「読みやすい」と感じるでしょう。
2. 同じ文末表現を繰り返していないか
文末表現とは、「〜です。」「〜ます。」などのことです。
基本的に文章を書く際は「ですます調」で作成すると思うのですが、「〜です。〜です。〜です。」や「〜ます。〜ます。〜ます。」など同じ文末表現が続いていると、読みづらさを感じると共に単調な印象を受けませんか?
改めて言葉にすると「当たり前」と思う方も多いとは思うのですが、実はこれって文章を書いていると意外と気付きづらいものです。実際にわたしも読み返したときに同じ文末が続いてた!ということがありますし、さまざまなサイトの記事を読んでいて「同じ文末続いていて読みづらい」と思うこともあります。
そんなときは「〜しょう。」や体言止めなどをうまく使って、同じ文末表現を繰り返さないようにすると良いかもしれません。
3. 一文が長すぎないか
文章を書いていると、少しでもたくさんの情報を提供したくて、一文に詰め込みすぎることがあると思います。しかし、長すぎる文章は理解しづらく、「結局どういうこと?」とユーザーを混乱させる原因になることも。
例えば、「文章を書いていると、少しでもたくさんの情報を届けたいという気持ちから、一文にたくさんの言葉をまとめてしまい、結果的に何が伝えたいのかわからなくなる時もあると思いますが、長すぎる文章は理解しづらいので文章を分けることが大切です。」など。
この場合、「①文章を書いていると一文にたくさんまとめてしまう」「②結果的に何が伝えたいのかわからなくなる」「③長すぎる文章は理解しづらいから分けよう」という3つの文に分けることができますよね。それぞれを一文として独立させてもよいのですが、「①+②」「③」で2つの文章に分けることもできます。
いくつかのパターンを試してみて、どの文章にしたら読みやすくなるかを考えてみるのもよいかもしれません。
4. 段落を分ける
段落を分けるって当たり前のことだとは思うのですが、無我夢中で文章を書いていると、気づいたら文章がかなりの塊になっていることありませんか? わたしはよくあります……。
そんなときは改めて文章を読み返して、3文ほどの段落に分けるようにしています。1つの段落に「何文まで」という決まりこそありませんが、できることなら3〜4文にまとめたほうが読みやすくなると思います。
ただし、改行のしすぎはかえって読みづらくなってしまうので、話が変わるときなどにあくまでも自然に改行することが大切です。適切に改行を使って読みやすくしていきたいですね!
5. 結論から書いているか
「順を追って話したほうがわかりやすいから結論は最後に書く」という方もいるかもしれませんが、基本的に結論→理由を書くのがベストなんだとか。
その理由は、「ユーザーは答えを求めて記事を読んでいるから」です。
ユーザーは忙しい合間を縫って記事を読んでくれているので、なかなか答えが出てこない(見つからない)記事だと離脱につながってしまいます。
それを踏まえると、結論から述べて理由を解説をしたほうが親切ですよね! 読み手の気持ちを考えながら記事を作成することで、自然と読みやすい記事になるのかもしれません。
より読みやすい記事を届けるためには「記事を育てる」ことが大事なのかも
記事は一度作成したらそれで終わりではありません。
より読みやすい記事にするために、定期的に見直して推敲(すいこう)する必要があるんです。※推敲とは……文章をよくするために何度も考えて作り直すこと。
具体的にいうと、現在記載されている情報を新しくしたり、追加したりすることを言います。
記事を書いていると、過去の記事に対して「やっぱりこっちの表現がよかったかな」「なんでこんな書き方したんだろう」ということもありますよね。わたしは結構あって、過去の自分の記事を読むたびに、「ここはこうすればよかった、ああすればよかった」という気持ちが出てきます。
そのようなところを修正することも大事なんですが、これはただの手直しであり、「記事を育てている」というものではないと考えています。
「記事を育てる」とはあくまでも、記事をよくするために情報を更新したり追加したりすることであり、ユーザーに読みやすさや鮮度の高い情報を提供するために考えたことや行動です。
これは自分にも言えることですが、記事のリライトを重ねる上でただの手直しになっていないか、しっかりと記事を育てることができているか、ということを考えながら対応していくことが重要なのではと思います。
まとめ
読みやすい記事に仕上げることは当たり前ではありますが、SEO対策として検索エンジンが評価しやすい記事ということを重視しすぎると、どうしても忘れてしまいがちです。
あくまでもユーザーに情報を届けることを前提として、その延長線上にSEO対策があると考えると良いのかもしれません。
今後もユーザーにとって読みやすい記事を意識して記事作成に取り組んでいきたいと思います。