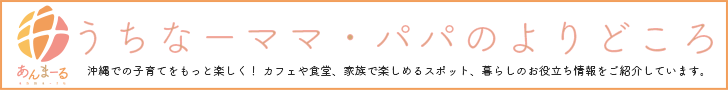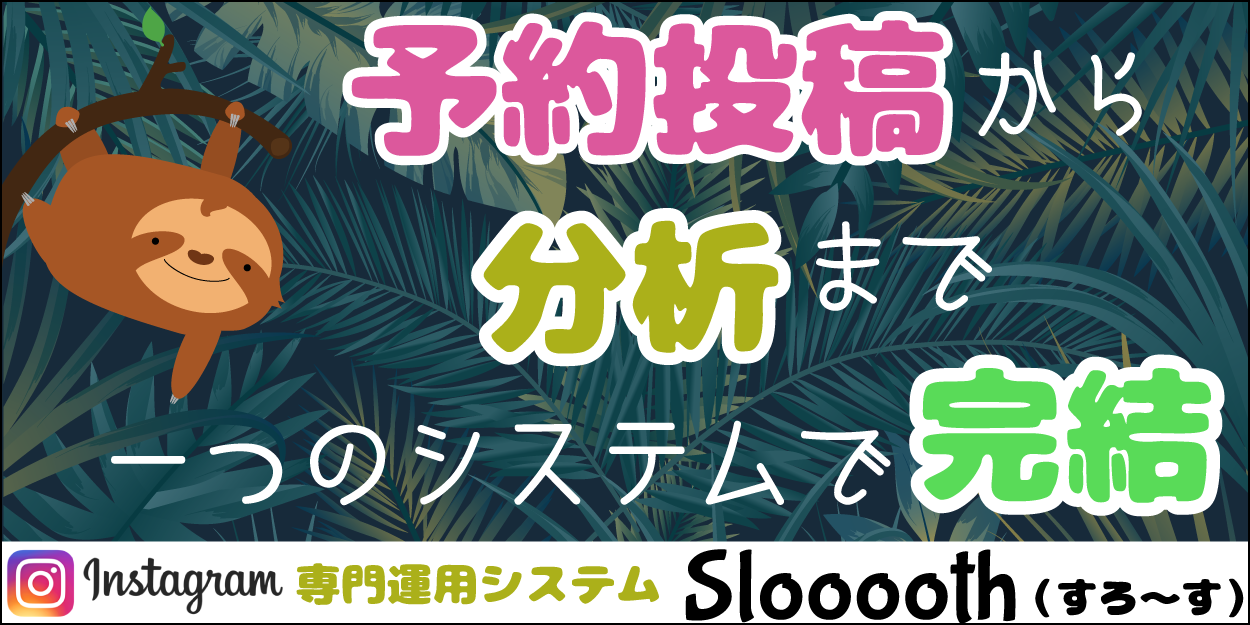記事の構成を考える際は「MECE(ミーシー)」を意識!その理由をわたしなりにまとめてみた
みなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
LOVELETTER WORKS 株式会社のゆーりんちーです!
情報の整理や分析に役立つフレームワーク「MECE(ミーシー)」をご存じですか?
主に、問題や課題の解決策を導き出す際に使われるそうですが、わたしは「記事の構成を考えるときにも使えるんじゃないか?」と思いました。
そこで今回は、わたしがMECEを意識したきっかけから、MECEの概要、記事の構成を考える際にどのようにMECEを使うのか、MECEを活用する際に役立つツールまで解説します。わたしなりの考えをまとめてみます!
目次
課題がきっかけ!MECE(ミーシー)を意識した出来事
そもそも、わたしはMECEをまったく知らなかったわけではありません。ただ、実際に業務で意識することはほとんどなく、なんとなく頭の中にある程度でした。
そんなある日、わたしのメイン業務である記事作成(正しくはリライト)をするなかで、ひとつの課題に直面しました。それは「構成を考える段階でもっと質のよい記事にできないか(リライトを最小限にできないか)」ということです。
記事は一度仕上げたら終わりではなく公開後もリライトしていく必要があるので、そういう意味ではいつでも質を上げられます。また、古い情報を最新の情報に直すことはどうしても必要になるので、リライトそのものをゼロにすることは絶対にできません。
ただ、リライトのなかでも追記がメインの場合は、「この情報が漏れていること、なんでライティング前に気付けなかったんだろう。最初から反映させたほうがよかったな」と思うこともあるんです。
記事が完成したあと何かを追記するのは、思ってるより手間です。忙しいタイミングでその作業をしなければならないとなると、より「構成の段階でできたはず……」と後悔してしまうことも。そのため、わたしは「なるべく最初から漏れのない、完璧に近い記事に仕上げたいな」と思ったんです。
「漏れなく……、そういえば漏れなくダブりなくってどこかで聞いたことあるな。あ、MECEだ!」
これが、わたしがMECEを意識したきっかけです。
一緒に理解を深めよう!MECE(ミーシー)とは
MECEは「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った言葉で、それぞれの単語には以下の意味があります。
- Mutually(お互いに、相互に)
- Exclusive(重複せず、被らず)
- Collectively(全体的に)
- Exhaustive(漏れなく)
つまり、MECEとは「互いに重複せず、全体として漏れがない」という意味であり、この考え方に沿って情報を整理することを指します。
とはいえ、重複せず漏れのない状態が具体的にどういうことなのか、なかなかイメージしづらいと思います。わたし自身、まだ理解しきれていない部分もあるので、以下で整理してみます。
MECEになっていないケース
MECEを理解を深めるには、MECEになっていないケースについて知るのが有効です。
重複はしていないが漏れがある
たとえば、とある商品のターゲットを「10代」「20代」「30代」に分類したとします。
この場合、それぞれは重複していませんが「10歳未満」「40代」「50代」「60代」などが含まれておらず、漏れがあることになります。
漏れはないが重複している
とある商品のターゲットを「大人」「子ども」「男性」「女性」で分類したとします。
この場合、「大人」と「子ども」それぞれに男女が含まれることになるので、漏れはないものの重複していることになります。
漏れているし重複もしている
例として、7歳〜20歳までを対象としたアンケートを実施するにあたって回答者を「小学生」「中学生」「高校生」「予備校生」「大学生」に分類したとします。
7歳〜20歳の人のなかには社会人や専門学生もいるため、まず漏れがあることがわかります。くわえて、中学生や高校生のなかに予備校生がいる場合もあるため重複もしているでしょう。
MECEになっているケース
上述したMECEになっていないケースのうち「重複はしていないが漏れがある」を例にあげて、MECEになっているケースをご紹介します。
おさらいすると、商品のターゲットを「10代」「20代」「30代」に分類した場合、「10歳未満」「40代」「50代」「60代」などが含まれていないため、MECEではないと解説しました。つまり、10歳未満も40代以上も含めればMECEになるということです。
そのため、商品のターゲットを「10歳未満」「10代」「20代」「30代」「40代以上」に分類すれば、誰もがいずれかの区分に該当するため、漏れがなくダブりもないMECEの状態となります。
ただし、対象となる商品が若年層向けのものである場合は、無理に40代以上を含める必要はありません。「商品のターゲットとして相応しい年齢層はどこまでか」を軸に、漏れがないかを確認するようにしましょう。
意識することが大切!MECE(ミーシー)が構成の質を高める
では、記事の構成を考える際にどのようにしてMECEを使えばよいのでしょうか? ここからはわたし独自の考えをまとめてみます。
結論からいうと、MECEを使うというよりは、MECEを意識するというのが正しいかなと思います。
繰り返しになりますが、わたしがMECEを意識したきっかけは「構成を考える段階でもっと質のよい記事にできないか(リライトを最小限にできないか)」と思ったことです。これはつまり、最初からなるべく漏れのない記事を作りたいという思いとイコールです。
ってなると、「SEO的にも読み物としても、この情報とこの情報があればいいんじゃね?」と比較的安易な考えで構成を作るのは違うなと。その考え方・進め方だと、きっと漏れが出てしまうだろうなと思うんです。
そこで、意識したいのがMECE! 「互いに重複せず、全体として漏れがない」という状態にする意識を持つだけで、記事の構成を組み立てるときに「この記事内で重複している情報はないか」「記事内に足りない情報はないか」などをより深く考えられるようになると思うんです。
たったこれだけのことを意識するだけでも、意識しない場合と比べてより質が高く、リライトを最小限にできる構成(記事)にできるんじゃないかなと思います。
【+α】記事作成中に文字数不足で困ったときも使えそう
構成を考えるときに限らず、記事作成中に困ったときにもMECEが役に立つなと思いました。
たとえば、記事を作成するなかで「文字数が足りない! 何か情報を足さなければ……」という状態になったとき、「記事内に足りない情報は何か」と漏れに焦点を当てて考えることで、意外とスムーズに加筆できるんじゃないかなと思いました。
お役立ち系やハウツー系の記事の場合、要素として王道なのは「メリット・デメリット」や「注意点(ポイント)」などですが、これらはMECEを意識しないでもスッと思いつくことがほとんどです。むしろ、MECEを意識しなければこれら王道の要素しか出てこず、なかなか加筆する情報が思い浮かばないなんてこともあるかもしれません。
MECEを意識することで王道以外に目を向けることができますし、読者に寄り添って「どういう情報が必要なんだろう?」と考えられるので、結果的によい記事に仕上がるんじゃないかなと思います。
めちゃくちゃ便利!MECE(ミーシー)を活用する際のお役立ちツール
SEOに携わっている人ならみんな知ってるんじゃないかというくらい有名な「ラッコキーワード」を最近よく使っているんですが、これがまぁ便利! MECEを意識・活用するという点でもかなり役立つので、最後にラッコキーワードの便利な機能とわたしなりに導き出したMECEを軸とした活用方法をご紹介したいなと思います。
関連キーワード
まずご紹介したいのは「関連キーワード」。SEOに携わっている人ならもう当たり前すぎる要素(?)かもしれませんが、MECEを意識するうえでこれはかなり便利です!
そもそも関連キーワードとは、ユーザーが検索したキーワードに関連するキーワードのことです。ユーザーがよく検索しているキーワードであり、とくに月間検索数が多いキーワードはユーザーニーズを表しているといえるため、SEOコンテンツを作成する際のヒントとして役立てられます。
たとえば、SEOの関連キーワードには「SEOとは わかりやすく」「SEOとは 初心者」「SEO 対策」「SEO対策 費用」などがあります。この結果から、SEOについてわかりやすく解説している記事が読みたいユーザーやSEO対策とはどういうものなのか、費用も含めて知りたいユーザーがいることがわかります。
このようにユーザーニーズを感覚的に掴めるため、記事の構成を考えるときに関連キーワードを使えば、漏れダブり、とくに漏れのない構成を組み立てることができます。
たとえば、キーワード「SEO」の記事構成を概要やメリット・デメリットなどの基本情報だけで組み立てていた場合は、関連キーワードにある「費用」を取り入れることで、漏れをカバーできます。
ただ、漏れをなくそうとするあまり要素を詰め込めすぎると、ボリューミーな記事になってしまう可能性があります。あまりにも長い記事だとユーザーが読み終わる前に離れる恐れがありますし(ジャンルにもよると思いますが)、多数のキーワードで上位表示を狙えなくなっちゃうので、1記事にどこまで要素を含めるかは検討しないといけませんね!
共起語
共起語とは、特定のことやものを説明する際によく使われる言葉・単語のことです。たとえば、メインキーワードがSEOだった場合、その共起語には「検索エンジン」「Google」「ランキング」「効果」「アルゴリズム」などがあります。
先ほど説明したように、共起語は「特定のことやものを説明する際によく使われる言葉・単語」なので、特定のこと・ものについて文章を書いていけば自然と網羅されます。そのため、記事の構成を考えるにあたって共起語を強く意識する必要はありません。
ただ、ユーザーニーズを読み解くための情報のひとつではあるので、関連キーワードと同じ考え方でチェックして、MECEに活かすことはできるのかなと思いました。
とはいえ、共起語には注意点がひとつ。
SEO対策の考え方として、前までは記事にキーワードの共起語を含めることが上位表示に効果的とされていましたが、検索アルゴリズムの精度が向上したことに伴い、最近は共起語の必要性がそこまで高くありません。そのため、過度に頼りすぎないよう注意しましょう。
記事見出し生成(AI)
記事見出し生成(AI)は、記事構成の草案を作成する際に便利な機能です。キーワードと簡単なタイトルを入れるだけで、ユーザーニーズを考慮した見出しをAIが自動的に生成します。
たとえば、キーワードを「SEO 対策」、タイトルを「SEO対策とは」にした場合は、以下のような見出しを生成してくれました。
| <h2>SEO対策とは?基本をわかりやすく解説</h2> <h3>SEOとは何か?その意味と重要性</h3> <h3>SEO対策の概要と目的</h3> <h3>初心者が知っておくべきSEOの基本知識</h3> <h2>SEO対策の種類と施策</h2> <h3>内部対策と外部対策の違い</h3> <h3>テクニカルSEOとその重要性</h3> <h3>効果的なキーワードの選定方法</h3> <h2>SEO対策の具体例と成功事例</h2> <h3>会社や自社のSEO成功事例</h3> <h3>ブログにおけるSEO対策の実践例</h3> <h3>成功したSEO施策の分解と分析</h3> <h2>SEO対策にかかる費用とは?</h2> <h3>SEO対策のコストとその内訳</h3> <h3>費用対効果を考慮したSEOの実践</h3> <h3>無料でできるSEO対策とその限界</h3> ・ ・ ・ |
これを叩き台にして、たとえば「関連キーワードの要素を含めた構成になっているか」をチェックして過不足を調整すれば、MECEも意識した、よりユーザーニーズに沿った記事構成が仕上がります。
ただ、一点注意したいのが、記事見出し生成(AI)に頼り切りにならないことです。丸々使ってしまうと文章は違えど構成がまったく同じなコピーコンテンツになってしまう可能性があります。それはなるべく避けたいので、自社ならではの要素・切り口を入れるなどの工夫が必要です。
【+α】自分ひとりで考えるだけでなく、ツールも頼るとよい
わたしだけかもしれませんが、「仕事は基本的に自分の頭で考えてこなさなければならない」というイメージがどこかにあります。だからこれまで、調べた情報を活用することはあっても、特定のツールを使うことはあまりありませんでした。
でも、それだとひとつの作業にかなりの時間を費やしたり、そもそも進め方が根本的に間違っていたりすることもあって非効率的です。
「自分で考えてこなす」という意識は決して無駄ではなく、むしろ持っていたほうがいいと思いますが、今はAIもかなり発達してたくさんの便利なツールが登場しています。そのため、もしこれらを使える環境なのであれば、常識の範囲内でどんどん活用していくべきだなと感じました。
実際、わたしは最近ラッコキーワードを使うようになってその便利さを体感しましたし、早く使いこなせるようになりたいなと思いました。頼れるところは頼って、考えるところは考えて、効率よく仕事を進めていきたいです。
まとめ
ある出来事とそれに伴う課題をきっかけに、MECEについてあらためて学び、理解を深めることができました。また、自分なりに思考を巡らせた結果、MECEは記事の構成を考える際にも役立つフレームワークだと気づけました。
記事に関しては、MECEの考え方でいうと「漏れがないか」がとくに重要だと、わたしは思います。漏れがないように意識して作成した記事は読了感が高まりますし、本来なら必要な情報がないという状態を避けられるため読者のニーズに応えたクオリティになります。また、わたしたち運営側にとってもリライトの手間が減るというメリットにつながります。
そのため、これからわたしは記事作成の基盤となる構成作成の段階で、MECEを強く意識していこうと思います。