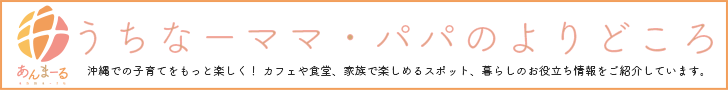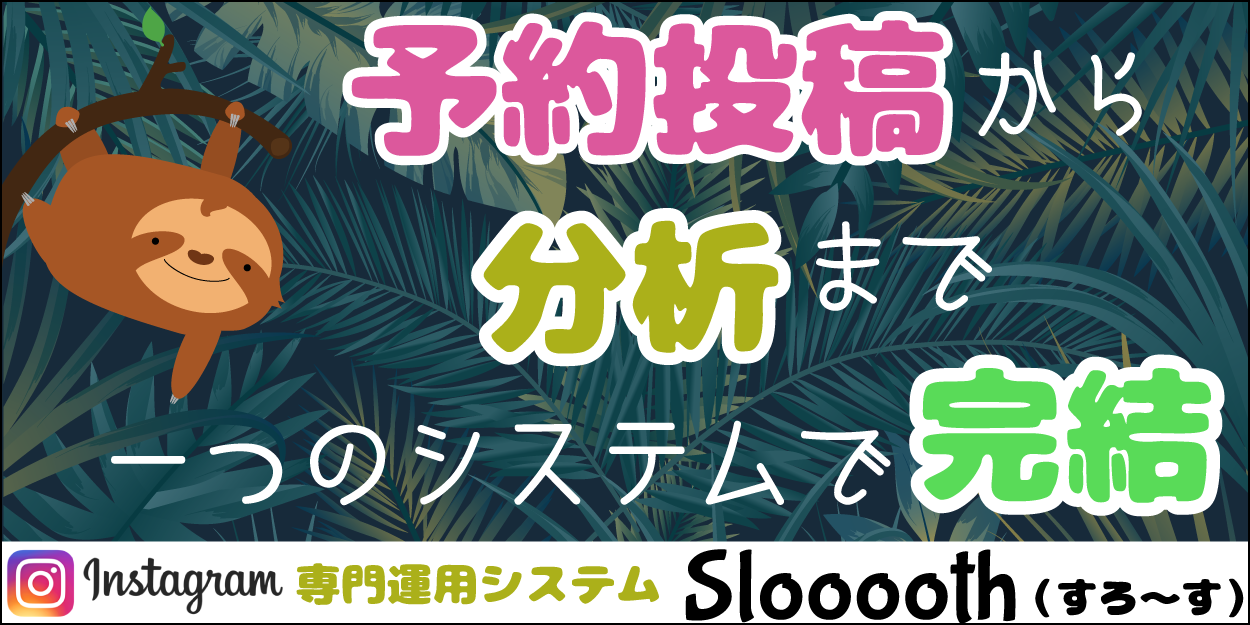仕事に感情は本当にいらないのか? ~感情を味方につけて、仕事も人生もレベルアップ~
皆さん、こんにちは! LOVELETTER WORKS 株式会社の篠原です。
お正月気分もすっかり抜け、日常に戻った方も多いのではないでしょうか? 年始の仕事始め、ちょっぴり憂鬱な気持ちになった方もいるかもしれませんね。
私たちは日々、様々な感情を感じながら生きています。 嬉しい、楽しい、悲しい、辛い… 仕事中だって、感情が湧き上がってくるのは自然なことです。
しかし、仕事では「感情的になるな」「冷静に判断しろ」とよく言われますよね。 確かに、感情に振り回されて衝動的な行動をしてしまうのは、良い結果に繋がりません。
とはいえ、だからといって感情を完全に無視してしまうのは、本当に正しいのでしょうか? 今回は、「仕事に感情は本当にいらないのか?」 というテーマについて、一緒に考えていきましょう。
目次
なぜ仕事に感情を持ち込むのはNGと言われるのか?
「仕事に感情を持ち込むな」と言われるのには、いくつかの理由があります。
感情は変わりやすいから
感情は、その時々の状況や気分によって大きく左右されます。 感情的な判断は、一貫性を欠き、安定した成果を出すのが難しい場合があります。
データや根拠に乏しく、的外れの可能性があるから
感情的な判断は、客観的なデータや根拠に基づいていないことが多く、的外れな結論に達してしまう可能性があります。
本来の目的から外れる可能性があるから
感情に左右されると、目の前の問題の本質を見失い、本来の目的から逸脱した行動をとってしまう可能性があります。
確かに、これらのリスクを考えると、感情に振り回されることなく、冷静かつ論理的に行動することの重要性は理解できます。
しかし、だからといって感情を完全にシャットアウトしてしまうのは、かえって逆効果になる可能性も秘めているのではないでしょうか?
感情を無視し続けることのリスク
確かに、感情的な行動は、時に問題を引き起こす可能性があります。 しかし、だからといって、自分の感情を完全に抑え込んでしまうのは、決して良いことではありません。
自分の感情を無視し続けると、どうなるでしょうか?
ストレスをため込みやすくなる
感情を押し殺していると、ストレスが蓄積され、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
自分を見失ってしまう
自分の感情に向き合わずに、周りの意見や状況に流されてばかりいると、本当の自分が分からなくなり、自信を失ってしまうかもしれません。
人間関係がうまくいかなくなる
自分の感情を表現できないと、相手に真意が伝わらず、誤解やトラブルが生じやすくなります。
「仕事に感情を持ち込むな」と言われると、まるで感情そのものを否定されているように感じてしまいますよね。
しかし、本当に問題なのは 「感情と行動を直結させてしまうこと」 なのではないでしょうか。
例えば、プレゼンで厳しい指摘を受けた時に、カッとなって反論してしまう。 これは、感情に任せて行動してしまった結果、起こるべくして起こったトラブルと言えるでしょう。
もし、その怒りの感情を一度受け止め、「なぜ自分は怒りを感じているのか?」「この怒りは何を意味しているのか?」 と自問自答する時間があれば、より建設的な行動を取れたかもしれません。
湧き上がる感情を、ただ抑え込むのではなく、 「理解する」 というステップを挟むこと。 これが、感情を 「やっかいなもの」 から 「自分を成長させてくれる武器」 へと変える鍵となるのです。
感情は成長のヒント
実は、感情は私たちに 「成長のチャンス」 を与えてくれる貴重な情報源でもあります。
例えば、仕事で「つまらない」「やりがいを感じない」という感情を抱いたとします。 これは、今の仕事内容に何か問題がある、あるいは、自分の才能や興味に合っていない可能性を示している可能性があります。 この感情をきっかけに、仕事内容を見直したり、新しいことに挑戦したりすることで、より充実したキャリアを築けるかもしれません。
逆に、「楽しい」「ワクワクする」という感情は、自分の強みや才能、興味を示しています。 この感情を大切に育むことで、さらにモチベーションを高め、パフォーマンスを向上させることができるでしょう。
感情を理解し、言葉にする
では、どのように感情と向き合えば良いのでしょうか? 重要なのは、自分の感情を 「正しく理解し、言葉にする」 ことです。
1. 感情の種類を知る
人間の感情は、実はたくさんの種類があるんです。 心理学者ロバート・プルチック博士が提唱した 「感情の輪」 を参考に、自分の感情を分析してみましょう。

感情の輪は、8つの 「一次感情」 (喜び、悲しみ、怒り、恐怖、信頼、嫌悪、期待、驚き) を基に、様々な感情が表現されています。 一次感情のうち2つが混合することで、さらに複雑な感情が生まれます。
例えば、「怒り」と「嫌悪」が混ざると「軽蔑」に、「喜び」と「信頼」が混ざると「愛」になります。
自分が感じている感情を、感情の輪と照らし合わせてみてください。 「モヤモヤする」といった漠然とした感情も、細かく分析することで、その中に隠された様々な感情に気づくことができます。
2. 日々の振り返りで、自分の感情に気づく
日々の業務を終えた後、 「今日、どんな感情を持ったのか?」 を振り返る時間を設けましょう。
「あの時、なぜイライラしたんだろう?」「あの仕事は、なぜ楽しかったんだろう?」
具体的な出来事と感情を結びつけて考えることで、自分の感情のパターンや、感情の トリガーを理解することができます。
3. 自分が持った感情を否定しない
「こんな感情を持つなんて、自分はダメだ…」 そうやって、自分の感情を否定していませんか?
感情は、あなたの過去の経験や思考に基づいて、自然に湧き上がってくるものです。 どんな感情も、 「あなたがあなたであることの証」 です。
「悲しい」「辛い」「腹が立つ」 そんなネガティブな感情も、否定せずに受け止めてあげましょう。 そして、「なぜ、そんな感情を持ったのか?」「この感情から、何が学べるのか?」 を考えてみてください。
感情を味方につけよう!
いかがでしたでしょうか?
感情は、時に厄介なものに思えるかもしれません。 しかし、自分の感情と真摯に向き合うことで、 新たな発見 や 成長のきっかけ を得られるはずです。
日々の感情の揺れ動きに意識を向けることで、
- 自分の興味や関心
- 課題意識
- 価値観
などが明確になり、より自分らしい行動を選択できるようになるでしょう。
さらに、自分の感情を理解できるようになれば、 相手の感情にも敏感になれる というメリットもあります。 これは、人間関係を築く上でも、マネジメントを行う上でも、大きな強みとなるはずです。
そして、何よりも 「自分を知る」 ことは、とても楽しいものです。 自分自身のことを深く理解することで、自信や心の安定に繋がり、より充実した人生を送ることができるでしょう。
2025年は、ぜひ 自分の感情と向き合う一年 にしてみませんか? きっと、仕事もプライベートも、より充実したものになるはずです。