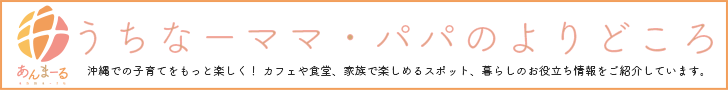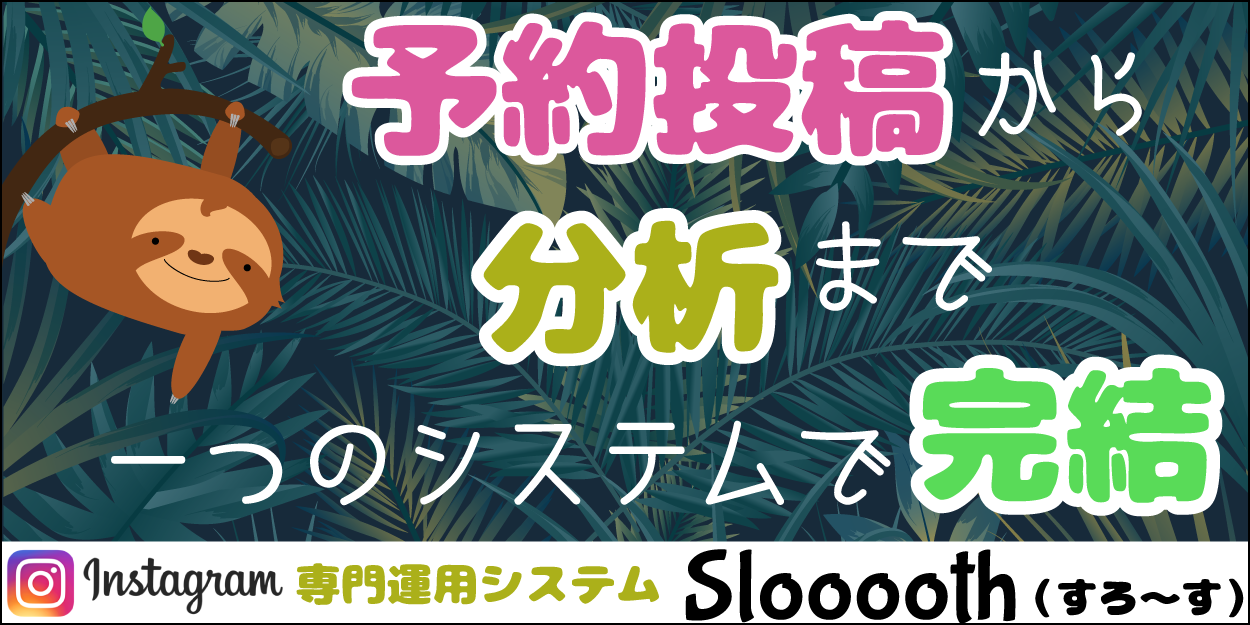後輩の育成でやるべきこと・やってはいけないこととは?
こんにちは。LOVELETTER WORKS株式会社の長浜です。
先日、中学のときの友達と会って最近の出来事について話を聞きました。友達が働いている飲食店に高校生のアルバイトが入ってきたのですが、なんと1日で辞めたとのこと。退職した理由は、「先輩が仕事を一気に教え込みすぎた」というものでした。
この話を聞いて、「うちの会社にも新しく人が入ってきたら気をつけなくちゃ……」と思ったので、自戒の念を込めて後輩育成のためにやるべきこと・やってはいけないことをまとめていきます。
目次
はじめに:「働き続けられるか」は人間関係によって変わる
個人的な意見ですが、その職場で働き続けられるかどうかは人間関係の要素が大きいと思っています。仮に、仕事がきつくても職場の人間関係が良ければお互いに励まし合ってがんばれると思うんです。反対に、仕事が簡単でも人間関係が良くないと居心地が悪く、職場で過ごす時間が億劫になってしまいます。
わたしは高校生のときのアルバイトを含め、これまで10社で働いてきました。このうち、人間関係を理由に退職したのは4社です。あとは、高校卒業・妊娠・会社の縮小などの理由で退職しました。
東京の飲食店で働いていたときは、「ここだけの給料じゃ生活できないよ」と愚痴をこぼしながらも、人間関係が良かったので掛け持ちをして働いていました。それぐらい、わたしのなかでは人間関係が仕事に大きく影響しています。
人によっては「給料が良ければ人間関係が悪くても良い」と思う人もいるでしょう。ですが、わたしのように人間関係を第一に考える人もいると思うので、今後入社してくる方に「良い会社に入社できた!」と思ってもらえるような環境づくりをしていこうと思います。
後輩育成のためにやるべきこと・大切なこと
では、後輩育成のためにやるべきこと、大切なことは何なのか。自分自身が「これをされたらうれしいな」と思うことを考えてみました。
1. お手本を見せる
わたしが高校を卒業して入社した会社では「率先垂範を心がけて」と教わりました。率先垂範は、人の先頭に立って模範を示すことです。基本的には初めて着手するものに関しては教わる&教えるのでクリアしているとは思います。
つい先日、初めての案件で取材の仕事があったのですが、行き慣れたカメラマンの方が店舗の担当者さまに挨拶をしてくれました。個人的にかなり助かったので、積極的にお手本を見せていこうと思います。
ただ、記事作成に関しては「過去の記事を見てみて」くらいしかできないので、たくさんアドバイスをできるように心がけます。
2. 褒める
過去にインターン生がおり、そのとき記事作成を対応してもらっていたので「ココいいね!」とコメントに残すことはありました。ですが、記事の作成本数が少ないこともあり、どちらかというと褒める機会はかなり少なかったです。それもあってか、早い段階でインターンが終了してしまいました。
個人的に、褒めることが苦手なので後輩ができたときは意識して褒めようと思います!
褒められるとモチベーションも上がりますもんね。これは後輩が仕事に慣れてきたあとも継続していけるようにがんばります。
3. 話しかけやすい雰囲気をつくる
対面だと「いまはかなり忙しそうだな。あとにしよう」と判断しやすいのですが、弊社はリモートなので相手の状況がわかりにくいことがほとんどです。わたしはもう職場に慣れたので「お手隙のときに話せますか?」とチャットを送ることができますが、入社したてはどうしても遠慮してしまうかもしれません。実際に、入社したてのころはチャットを送るのをためらっていました。
過去に同僚が「忙しそうだからって遠慮しなくていいよ!8時間働いているうちの数分でしょ?時間ないわけがない!」と言っていました。個人的にその言葉を聞いて話しかけるハードルが低くなったので、後輩ができたときは真っ先にそれを伝えようと思います。
あと、仕事中は基本的に仕事の会話しかしないのと、顔を合わせる回数が少ないのでできる限りコミュニケーションを取れるようにがんばります。過去の記事でも記載したとおり、コミュニケーション不足は「意見しづらい環境」になってしまうと思います。自分が忙しいとどうしても放置しがちになってしまうので、相手に配慮しつつ話しかけていけるようにします。
後輩の育成でやってはいけない5つのこと
わたしが後輩育成でやってはいけないと思うことは以下の5つです。
1. できて当然と思い込む
自分にとっての「できて当然」は、相手もそうとは限りません。人によって得手・不得手はあるものです。たとえば、わたしはエクセルの関数がかなり苦手です。関数に詳しい人からすると、「どうしてそんなこともできないの?」と思うかもしれません。しかし、その意見の押しつけは相手にプレッシャーを与えます。
また、「できるだろう」という思い込みで期待してしまっている分、相手がミスしたときにイライラしてしまう可能性もあります。もし相手にそのイライラが伝わってしまった場合、「働きづらい職場」と思われてしまうでしょう。
イライラはしないものの、わたしは「わかるだろう」と思い込んでしまうことがあります。これが相手のプレッシャーになる可能性はあるので、思い込みで対応しないように気をつけます。
2. 叱るときに相手の人格を否定する
叱る機会はほとんどないと思いますが、いつかは叱ることもあるかもしれません。わたしが上司から学んだことは「相手の人格を否定する叱り方はしないで」でした。
相手の人格を否定する叱り方として、たとえば相手が遅刻をした場合に「社会人失格」という言葉が挙げられます。たしかに、社会人として時間を守ることは重要です。だからといって、社会人失格と言われるとモチベーションが下がりますよね。
叱る際は、相手の性格や能力ではなく、事実のみに焦点を当てる必要があります。遅刻が多いのであれば、なぜ遅刻するのか原因を探り、一緒に解決策を考えるほうが後輩は育っていくと思います。
3. 接し方が不平等
後輩が2人以上いる場合、注意したいのが平等に接することです。たとえば、「仕事をそつなくこなすAさん」「がんばっているけど仕事がうまくいかないBさん」の2人がいるとします。この場合、辞めてほしくないという思いからAさんのほうをかわいがってしまうかもしれません。
もし、Aさんには丁寧に仕事を教え、Bさんにはイライラしながら仕事を教えていたらどうでしょうか?Bさんはモチベーションが下がってしまいますよね。
わたしは「接し方が明らかに違う。この職場に自分の味方はいない」と感じて仕事を辞めたことがあります。人間なので情が入ってしまうこともあるかもしれませんが、後輩が2人以上入ってくる場合は平等に接するように心がけます。
4. 一気に教え込む
忙しいと、できれば1つでも多くの仕事を覚えてもらいたいと思うかもしれません。しかし、一度に理解できる内容には限界があります。一気に詰め込んで教えると、相手がパニックになってしまう可能性があります。
冒頭でお伝えした辞めたアルバイト生は一気に教え込まれたからパニックを起こし、泣いてしまったそうです。一気に教え込まれると覚えられないうえに、「聞いたら怒られるのでは……」と不安になってしまうので、その人のペースに合わせて教えていく必要があります。
5. 先回りして自分の意見を言う
自分が考えていること・考え方について教えるために、最初は先回りして自身の意見を言うのは問題ないと思います。たとえば、「PV数を増やすためには?」というテーマで後輩と話し合ったとします。このとき、最初であれば自身の意見を伝えることで「こういう考え方もあるのか」と勉強になるでしょう。しかし、毎回先に自身の意見を伝えていると相手が思考しなくなる可能性があります。
過剰に手取り足取り教えすぎると、自立する機会を奪うことになります。何でも先輩に確認しないと動けない状況をつくってしまうことになるため、後輩が主体的に考えて行動できるよう、適度な距離感を保つことが重要です。
まとめ
アルバイト生が1日で辞めた話を聞いたとき、「いまの若い子は……」という意見がありましたし、わたしもそう思いました。ですが、年齢に限ったことではないんですよね。パワハラと指摘されやすいいまの時代、後輩に注意できない人が増えており、人によっては「注意されないから自分の成長につながらない」と退職する方もいるそうです。
「注意されたから辞める」という人もいてなかなか難しいですが、個人に合わせてサポートしていけるようにがんばります。