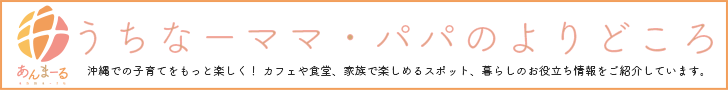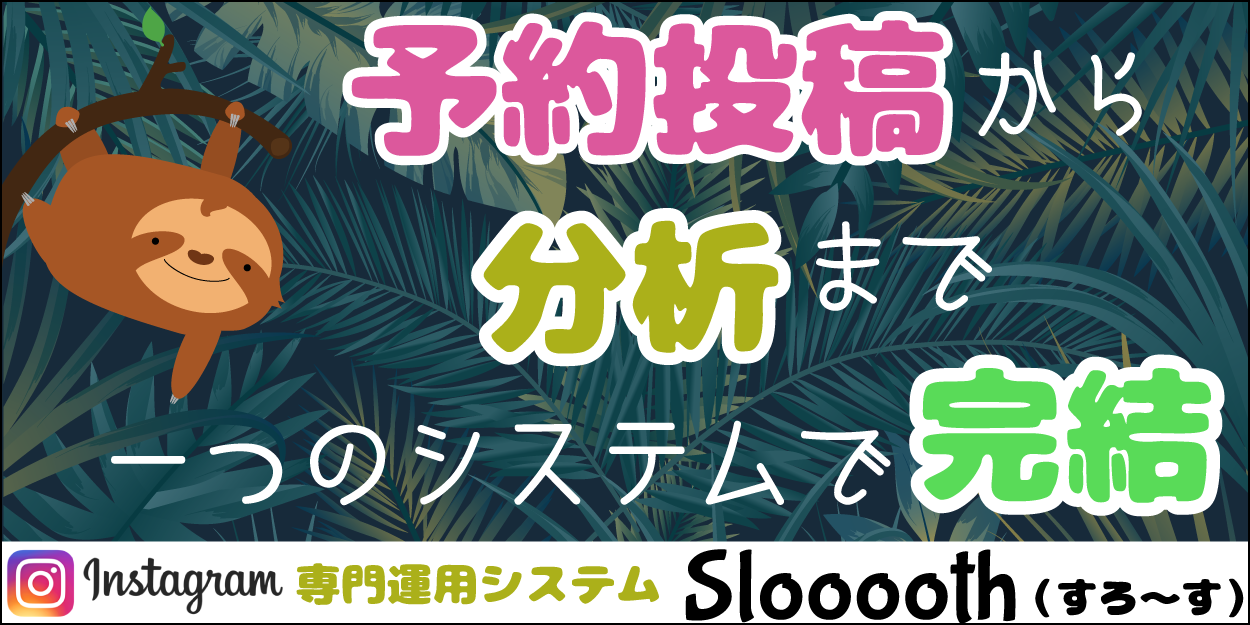4月からのスタートダッシュに備えて。知っておきたい自分の「やる気スイッチ」
皆さん、こんにちは! LOVELETTER WORKS 株式会社の篠原です。
もうすぐ4月、新しい環境でのスタートが近づいてきましたね。部署異動、昇進、新しいチームでのマネジメントなど、変化の多い時期だからこそ、期待と同時に少しだけ不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私自身、20代の頃は環境の変化に戸惑うことが多く、責任感から無理をしてしまい、ゴールデンウィーク明けに疲れがどっと出てしまった経験があります。そんな経験もあり、今のうちから「自分のやる気スイッチ」を理解しておくことの大切さを実感しています。
自分のモチベーションの源泉を知ることは、新しいスタートをスムーズに切り、その後のパフォーマンスを高める上で非常に重要です。また、チームを率いる立場としては、メンバーそれぞれの「やる気スイッチ」を把握し、最大限に能力を引き出すことが、チーム全体の成果に繋がります。
今回は、「内発的動機」と「外発的動機」、そして「自己効力感」「自己有用感」「自己肯定感」という3つのキーワードを軸に、自分自身とチームの「やる気スイッチ」をどのように見つけ、活用していくかについて、詳しく掘り下げていきたいと思います。
目次
1. モチベーションの源泉を知る:「内発的動機」と「外発的動機」
人の行動の原動力となるモチベーションは、「内発的動機」と「外発的動機」の2つに大きく分けられます。
1-1. 内発的動機:内面から湧き上がる興味・関心
内発的動機とは、好奇心や興味、達成感など、自分の内側から湧き上がる欲求によって行動するモチベーションのことです。「楽しいからやる」「もっと知りたいからやる」といったように、行動そのものが目的となります。
内発的動機によって行動しているときは、集中力が高まり、創造性が発揮されやすいと言われています。また、困難な課題にも粘り強く取り組むことができるため、長期的な成長にもつながりやすいと言われています。
私は、昔から人の心の動きに強い興味があり、心理学や行動経済学に関する書籍を読むのが好きでした。仕事においても、組織運営・マネジメント・マーケティングの分野に関しては、今でもわくわくとしながら仕事に取り組んでいます。
1-2. 外発的動機:アメとムチで高まるモチベーション
一方、外発的動機とは、報酬や評価、罰則など、外部からの刺激によって行動するモチベーションのことです。「給料を上げるために頑張る」「怒られないようにやる」といったように、行動はあくまで手段であり、目的は評価や報酬を得ることです。
外発的動機は、短期的には効果を発揮しやすいですが、長期的に持続させるためには、継続的な刺激が必要となります。また、外発的動機ばかりに頼ると、創造性や自発性を発揮しにくい可能性があります。
私自身、20代前半の頃は「怒られたくないから頑張る」という外発的動機で仕事に取り組んでいました。とにかく自分の意思がなく、常に「正解」を出そうと、メール一つ送るのにも上司の顔色を窺い、びくびくしていたのを覚えています。
もちろん、褒められれば嬉しかったのですが、完全に自分の興味関心よりも上司の評価に意識が向いており、仕事が全く楽しいと感じられませんでした。今振り返ると、あれはまさに外発的動機に振り回されていた時期だったと思います。
1-3. バランスが重要:内発的動機と外発的動機の組み合わせ
どちらの動機も、状況や課題によって有効性が異なります。重要なのは、両方の動機をバランス良く組み合わせることです。
例えば、新しいプロジェクトに取り組む際には、まずは内発的な興味や好奇心を刺激し、自主的な取り組みを促します。そして、適切なタイミングで成果を評価し、報酬を与えることで、外発的な動機も高めていくといった感じです。
内発的動機と外発的動機の話でふと思い出したのが、昔の先輩から言われた言葉です。当時、自分の仕事が手一杯で部下の育成まで全く手が回らず、「マネジメントやりたくないな〜」と思っていた時のこと。トップセールスで自分自身でガツガツ営業をしていた先輩が、昇格しマネジメントに携わるようになり、気づくと数十名の部下を抱えていました。
その先輩に「マネジメントってもともと興味ありました?会社から求められてやるの大変じゃないですか?」と聞いたことがあるんです。そうしたら、「正直もともと興味はなかったよ。けど、昇進昇格していくと、どんどん自分の興味のない仕事も振られるようになる。大事なのは、そこで自分がやる動機を自分自身でつくること。」
その時に、どんなことにも自分が能動的に取り組む意義や面白いと思うポイントを自分で見つけられること(内発的動機を作る)ができれば、どんな環境・どんな仕事でも前向きに頑張れるのでは、と思いました。
つまり、外発的動機で与えられた役割や仕事に対して、内発的動機を掛け合わせることで、どんな環境でも最大限のパフォーマンスを発揮できるのだと、先輩の言葉を思い出す度に思います。
2. 3つの「自己〇〇感」を高めて、やる気を持続させる
モチベーションを維持し、パフォーマンスを最大限に発揮するためには、「自己効力感」「自己有用感」「自己肯定感」という3つの「自己〇〇感」を高めることも重要です。
2-1. 自己効力感:自分ならできる!という感覚
自己効力感とは、「自分ならできる」という感覚のことです。過去の成功体験や、他者からの励ましなどによって高まります。自己効力感が高い人は、困難な課題にも積極的に挑戦し、粘り強く努力することができます。
2-2. 自己有用感:自分の行動が誰かの役に立っているという感覚
自己有用感とは、「自分の行動が誰かの役に立っている」という感覚のことです。他者からの感謝や、社会への貢献などを通じて高まります。自己有用感が高い人は、仕事にやりがいを感じやすく、積極的に貢献しようとします。
2-3. 自己肯定感:ありのままの自分を肯定する感覚
自己肯定感とは、「ありのままの自分を肯定する」感覚のことです。自分の長所だけでなく、短所や失敗も受け入れ、自分を尊重することで高まります。自己肯定感が高い人は、精神的に安定しやすく、ストレスにも強くなります。
相互に影響し合う3つの「自己〇〇感」
これらの3つの「自己〇〇感」は、相互に影響し合っています。例えば、自己効力感が高まると、新しいことにも積極的に挑戦できるようになり、その結果、自己有用感や自己肯定感も高まります。
3つの「自己〇〇感」を高めるためには、日々の小さな成功体験を積み重ねたり、他者からのフィードバックを積極的に受け入れたり、自分の良いところを見つけて認めるなど、意識的な取り組みが重要です。
3. マネジメントへの応用:チーム全体のモチベーションを高める
自分のやる気スイッチを理解することは、自分自身のパフォーマンス向上だけでなく、チーム全体のモチベーションを高める上でも非常に役立ちます。
3-1. メンバーの「内発的動機」を刺激する
メンバー一人ひとりの興味や関心、価値観を理解し、彼らの内発的動機を刺激するような仕事や役割を与えることが重要です。
例えば、新しい技術に興味を持っているメンバーには、その技術を活かせるプロジェクトに参加させたり、マネジメントに関心があるメンバーには、積極的に後輩育成に取り組んでもらうなどがあります。
3-2. 適切な「外発的動機」を与える
外発的動機も適切に活用することで、メンバーのモチベーションを高めることができます。
例えば、目標達成に応じて報酬を与えたり、優れた成果を上げたメンバーを表彰したり、キャリアアップの機会を提供などが考えられます。
ただし、外発的動機だけに頼ると、メンバーの自律性や創造性を損なう可能性もあるため、注意が必要です。
3-3. 3つの「自己〇〇感」を高める支援をする
メンバーの自己効力感、自己有用感、自己肯定感を高める支援をすることも重要です。
例えば、目標を達成しやすいように、段階的に課題を与えたり、成功体験を振り返り、自信をつけさせたり、日頃から感謝の気持ちを伝え、貢献を認めたり、フィードバックをする際に、良い点と改善点を具体的に伝え、成長を支援するなど、こまめなコミュニケーションを通じて、相手の自己〇〇感を刺激します。
まとめ:自分のやる気スイッチを理解し、最高のパフォーマンスを
「仕事にモチベーションなんていらない」
そんな言葉を耳にすることがあります。確かに、仕事は趣味ではありません。自分の好き嫌いだけでお客様に最高のサービスを提供できないのは、プロとしてあってはならないこと。
でも、私たちはロボットではありません。天気や気温に左右されたり、昨夜見たドラマに感動したり、友人との些細な喧嘩にモヤモヤしたり…感情の波は日々変化しますし、体調だって毎日同じとは限りません。
だからこそ、「自分がどんな時にやる気になるのか」を知り、ある程度コントロールすることが、ビジネスパーソンとして大事なんじゃないかなと思うのです。
やらなければ…と義務感で取り組むよりも、やりたい!と意欲的に仕事をした方が、パフォーマンスが向上するのはもちろん、何より自分自身が楽しいはずです!
4月、最高のスタートダッシュを切るために、少しだけ自分の内側を覗いてみませんか?