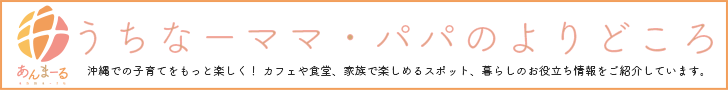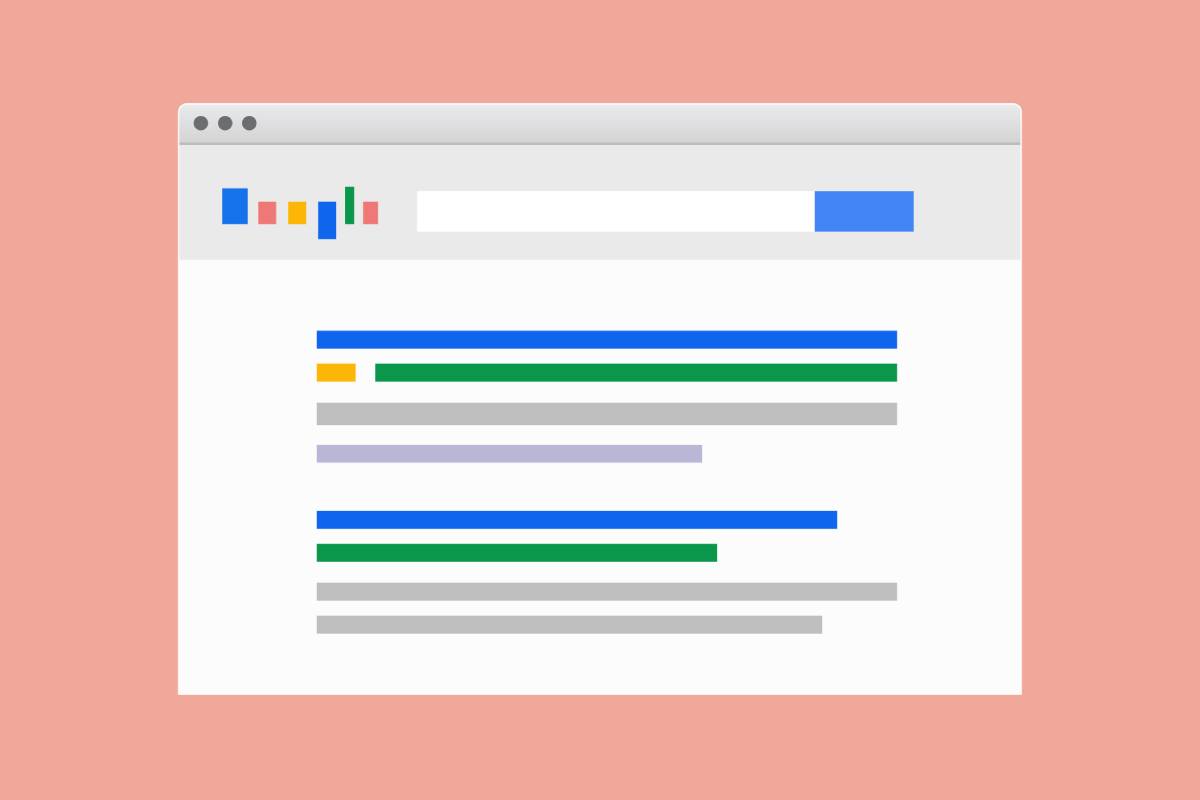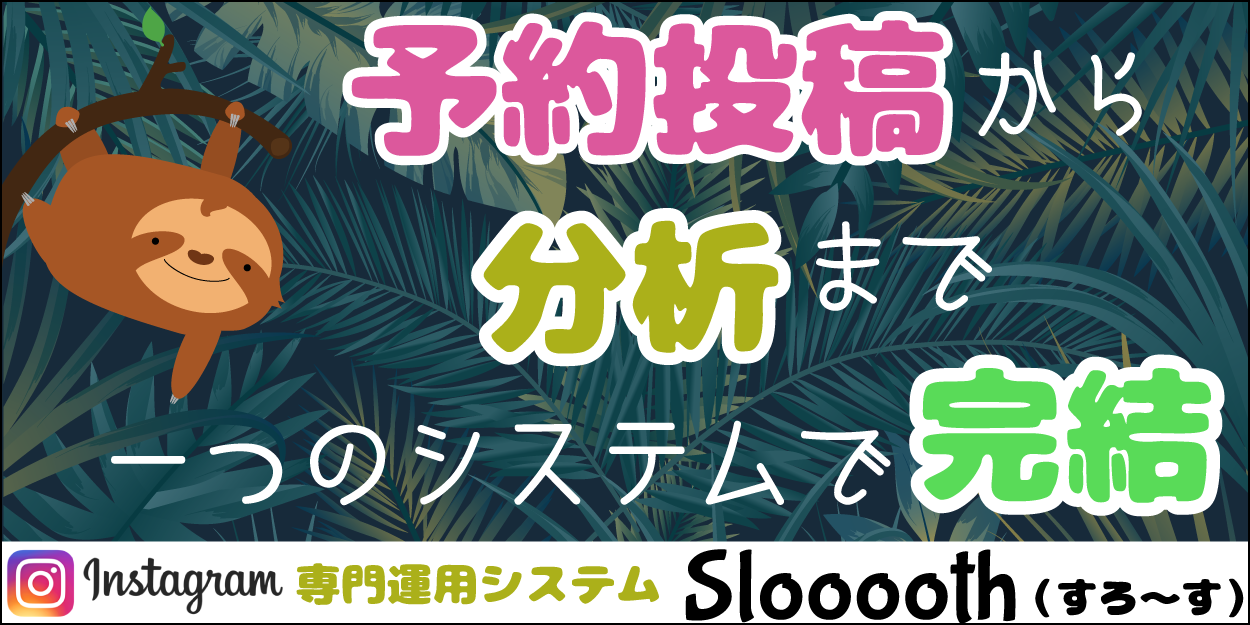思考の質を高める「具体と抽象」とは?手軽にできるトレーニング方法について
こんにちは。LOVELETTER WORKS株式会社の長浜です。
わたしは仕事をしていて「自分は視野が狭いな」と思うことがあります。知識や経験の部分もあると思いますが、考え方が影響していることもあると思うんです。
そこで視野を広げる方法を考えたときに、以前上司から教わった「具体と抽象」を思い出しました。この具体と抽象の考え方が身につけば仕事に大いに役立つと思うので、トレーニング方法を調べてみることに。今回は、具体と抽象について調べた結果をまとめていきます。
目次
ビジネスに役立つ「具体」⇄「抽象」
「具体」とは、目の前にある現実的な事実やデータ、詳細な情報を指します。「リンゴ」という単語を聞くと、赤い果実、甘酸っぱい味などのイメージが頭に浮かぶでしょう。これが「具体」のレベルです。
一方で「抽象」は個別の事例から共通点を見出し、より汎用的な概念にまとめたものです。「果物」という言葉は、リンゴやバナナ、オレンジなどを含む広い概念です。
具体的な事実から抽象的な原則を導き出し、また抽象的な原則を具体的な実例に応用することで、以下の効果が得られます。
・視点が広がってアイデアを得られる
・コミュニケーション力が向上する
・問題解決や意思決定がスムーズになる
わたしは視野を広げたいので、「視点が広がってアイデアを得られる」に焦点を当て、どのように考え、なぜビジネスに役立つのかをまとめていきます。
「具体」⇄「抽象」がビジネスに役立つ例
たとえば、自分がお菓子を製造する人だとします。ヒット商品を生み出したいけど、パッとアイデアが出てくるわけではありません。仮にアイデアが出てきたとしても、それがヒットするかどうかは賭けです。「この商品ならヒットする」ということを裏付けるデータがないと、上司から承認されないかもしれません。そこで役立つのが「具体」と「抽象」です。
1.現在の人気商品を具体化する
まず、既存の人気のある商品について、特徴を具体的に書き出します。
・チョコレート
・口溶けが良い
・甘さ控えめ
・持ち歩きやすい
具体的な特徴をできるだけ詳細にリスト化し、商品がどう受け入れられているか、どのようなときに選ばれるかを明らかにします。
2.抽象化する
次に、上記の具体的な特徴を抽象化してみます。「この商品が人気な理由は?」「どうしてこの特徴が求められているのか?」という視点で考え、特徴の背後にあるニーズや価値観に目を向けます。
・手軽さ
・日常で楽しめる
・気軽に贅沢気分を味わえる
ここでは、「なぜこの商品が選ばれるのか」を抽象的な価値や概念に落とし込みます。
3.抽象から新しい具体案を構想する
抽象化した情報をもとに、新しい商品アイデアを構想します。
たとえば「手軽さ」に着目した場合、味を変えなくても外出先でも食べやすいサイズに変更すれば、ヒットするかもしれません。
わたしはキットカットが大好きなのでそちらを例に出すと、キットカットは同じ味でもサイズが違う商品がいくつか出ています。長方形で大きいキットカットバーは贅沢感がありますし、小さいサイズは個包装されているのでみんなと分け合って食べることができます。一口サイズは、一口で食べられるのでポロポロ落ちないしかなり手軽に食べられます。
このように、抽象化の段階で浮かんだ価値やニーズにもとづき、少し異なるタイプの商品や味、形状、パッケージデザインなどの具体案を検討します。
「具体から抽象、そして再具体化」というプロセスを通じて、新たな商品アイデアをより自由で広範に検討できるようになるのです。
新商品のアイデアだけではなく、すでにある商品をアピールしたいときにも「具体」と「抽象」が役立ちます。たとえば美容化粧品をアピールしたい場合、具体だと「◯◯(成分)が入っているから肌にハリと透明感を与えられる」「寝る前に使用すると翌朝の肌がふっくら」、抽象だと「透明感のある肌へ導く」「肌が整うことで気分が上がる」というように、具体で商品の機能と効果、抽象で感覚や満足感を伝えることで製品のメリットを多面的に訴求できます。
「具体」⇄「抽象」のトレーニング方法
わたしは「覚えるとき」は自然と具体と抽象を使っているのですが、「考えるとき」はまだ瞬時に使えません。
覚えるときとは、以下のようなイメージです。
例)6匹の生き物を10秒で覚えてください。
| スズメ | イルカ | ウサギ |
| サメ | カラス | パンダ |
上記は「具体」です。これを抽象化していきます。
・陸の生き物:2
・海の生き物:2
・空の生き物:2
再度、具体化していきます。
・陸の生き物:ウサギ・パンダ
・海の生き物:イルカ・サメ
・空の生き物:スズメ・カラス
ビジネスで役立つのは「考えるとき」なので、どのようなトレーニング方法があるのか調べてみました。下記にまとめていきます。
トレーニング方法1:具体と抽象の言い換え練習
好きなテーマや物事をひとつ選んで、具体と抽象を言い換えるトレーニング方法です。
ここでは、わたしの好きな「コーヒー」をテーマに具体と抽象を行っていきます。
コーヒーを具体化していくと、「エスプレッソ」「カフェラテ」「モーニングコーヒー」などが挙げられます。
続いて、これらの事例に共通するものを探してみます。「リフレッシュするもの」「カフェインが含まれているもの」などが挙げられます。
最後に、「カフェインが含まれているもの」という抽象的な概念を使って、今度は別の具体例を出していきます。カフェインが含まれているものには、たとえば紅茶やお茶などがあります。今度は「紅茶」をテーマに具体と抽象を言い換えていく、というトレーニング方法です。
トレーニング方法2:質問で考えを掘り下げる
新しい商品を開発する場合、「どうしてその商品を作りたいのか?」と問いかけ、答えが出たらさらに「どうして?」を繰り返すトレーニング方法です。
抽象的な考えが出た場合は、「具体的にはどうする?」と質問して細かいアクションに落とし込んでいきます。
この「どうして?」と「具体的には?」を繰り返すことで、考え方の幅が広がります。
トレーニング方法3:会話での実践
たとえば「旅行」について話し合うとします。「旅行先で美味しいものを食べた」という話から始め、相手の話に応じて「非日常体験がリフレッシュになる」という抽象的な話に発展させてみます。相手が具体的な話をしたら抽象的に返す、逆に抽象的な話を聞いたら具体例を挙げて返すなど、具体と抽象の視点を意識しながら進めるトレーニング方法です。
これは社内でのトレーニングに良さそうですね。
まとめ
頭が良いといわれる人は、具体と抽象の考え方ができているから1を聞いて10を知ることができるのだそうです。具体と抽象の考え方はアイデアを出したいときや問題を解決したいときなどビジネスに役立つので、まずはちょっとした空いた時間に1人で具体と抽象の言い換え練習を行っていこうと思います。