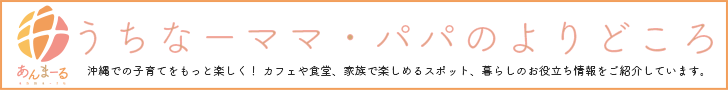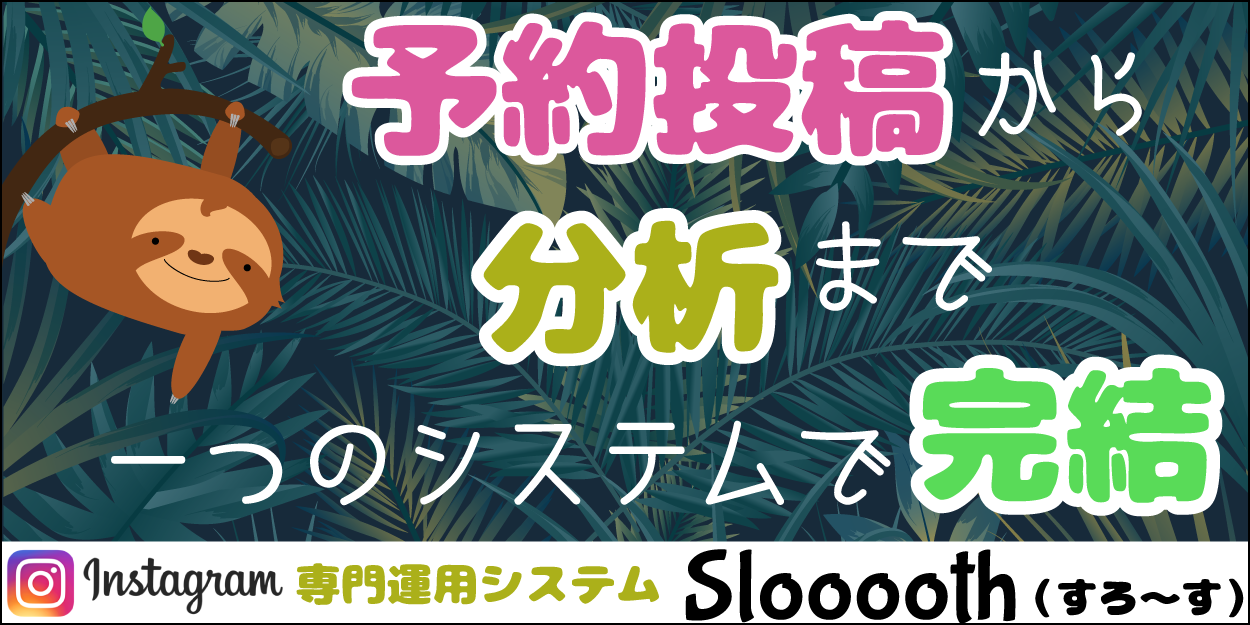残業を減らすことにつながる!ビジネスで意識したい「パーキンソンの法則」と「ツァイガルニク効果」
みなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
LOVELETTER WORKS 株式会社のゆーりんちーです!
よく「残業になる原因は、効率的に仕事ができていないから」と見聞きしますよね。ここ数か月の間に残業が当たり前になってきたので、最近この言葉についてよく考えます。
シンプルに仕事の量が多い、繁忙期が続いている、人手不足、業務が属人化しているなど、いろいろ原因はあるかもしれませんが、早急に改善を図るならやっぱり自分を見直すしかありません。
ということで今回は、今の自分にできる「残業を減らすために意識したいこと」にはどのようなものがあるか考えてみようと思います。
目次
だから減らしたい!わたしが残業したくない2つの理由
そもそも、残業が好きな人っているんですかね?(笑)
まぁ、仕事が好きでずっとやってられるって人はいるかもしれませんが……。
わたし自身は、残業が好きではありません。そう思う理由は主に2つあります。
1.長く仕事しすぎると頭が働かなくなるから
何事も長くやりすぎると疲れるものです。仕事も同じで、朝から夜までずーっとしていると疲れてきます。わたしの場合、頭が働かなくなってくるので、とくに思考を伴う仕事(例:Webライターでいうとキーワード選定や記事作成、記事やメディアの効果検証など)はスムーズにできなくなります。
◯ 関連記事
差し込み仕事はなくならない!わたしが考えた上手な付き合い方をご紹介
仮に、残業して思考を伴う仕事をやり遂げたとしても、翌日見直してみたら「なんだこれ?」という仕上がりなこともあり、この場合は修正にかなりの時間を要します。二度手間になるうえに、業務時間を修正作業に費やしてしまい、その日もまた残業するという悪循環が生まれてしまうんです。
こうした事態を防ぐためにも、なるべく業務時間内で仕事を切り上げたいなと思います。
2.「平日=仕事しかしない日」になるから
日々生活するなかでやることってたくさんあるじゃないですか? たとえば、料理に洗濯、お風呂、スキンケア、ストレッチ、お子さんがいれば育児など。これに加えて、ドラマや映画を観たり漫画を読んだりと、自分の好きなことをする時間も確保できるとうれしいですよね。
でも残業が続くとそれがなかなかできません。もちろん、朝早く起きていろいろ済ませたり趣味を楽しんだりするのも一案ですが、睡眠時間を短くするとなるとそれはそれでしんどくなります。
そのため、残業が続くといつの間にか「平日=仕事しかしない日」になっちゃうことがあるんです。
寝て起きて仕事して、ご飯を食べて仕事してまた寝る……。リフレッシュする時間がまとまって取れないのはなかなか辛いものです。
個人的にはこのライフスタイルが好きではないので、やっぱり業務時間内で仕事を切り上げたいなと思います。
心理効果を活用!残業を減らすために意識したいこと
残業は仕事に支障をきたす可能性があり、自分のメンタルにも影響を及ぼしかねません。もちろん、どうしても必要な残業もあると思いますが、それ以外はなるべく減らしていきたいものです……。
残業を改善する一番手っ取り早い方法は、自分の仕事の仕方や考え方を変えること。
これまでにも「自分のタスクを明確にする(月ごと・日ごと)」「タスクに優先順位をつける」など、工夫を凝らしてきましたが、もしかしたらまだまだ足りないのかもしれません。
そこでいろいろ調べてみたところ、「パーキンソンの法則」「ツァイガルニク効果」という2つの心理効果に出会いました。これが結構使えそうなので、ここでご紹介します。
1.パーキンソンの法則を意識する
パーキンソンの法則とは、イギリスの政治学者・歴史学者であるシリル・ノースコート・パーキンソンが、組織・運営と人間の心理作用に関する非合理的な行動について説いた法則です。第一法則と第二法則の2つがあり、そのうち残業の削減に関係するのは第一法則です。
パーキンソンの法則 第一法則
「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」
簡単にいうと、「本来なら2時間で終わるはずの業務も、締め切りが設けられていない、または締め切りまでだいぶ時間がある場合、その与えられた時間をまるっと業務にあててしまう」ということ。仮に早めに着手したとしても、「まだ時間がある」とほかの業務に移ったり後回しにしたりして、なかなか完成させられなくなるんです。
これは言い換えれば、「締め切りをこまめに設ければ比較的早く業務を終わらせられる」ということです。与えられた時間が少ないとわかっていれば、どうにかして終わらせようと工夫するため、効率よく仕事を進めることができます。それが結果的に残業の削減につながるのです。
わたしの場合、基本的に各タスクの本納期を基準に動いていて、自分だけの日ごと・週ごとの締め切りは設けていませんでした。そのため、その日のタスクが終わらなかったときは「明日でいっか」と自分に甘く対処していたことも……。
これが残業につながるきっかけだったかもしれないので、今後はパーキンソンの法則 第一法則を意識して、日・週単位で締め切りを設けて守るようにしたいなと思います。
2.ツァイガルニク効果を利用する
ツァイガルニク効果とは、やり遂げたことよりもやり遂げられなかったこと、または中断していることのほうが記憶に残る現象のことです。
たとえば、「キリのよいところまで終わっている仕事」と「中途半端に着手した仕事」がある場合、前者はひと段落ついているので安心感が増し、その後あまり気にならなくなってしまいます。
一方で、後者はひと段落ついていないのでモヤモヤが残り、自然と意識・着手することが増え、結果的に効率よく進められます。これがツァイガルニク効果です。
わたしは本来なら、ひとつのタスクを完璧にこなしたあと次のタスクに移りたいタイプです。でも、ツァイガルニク効果を軸に考えるとそれは非効率。とくに記憶に残る「やり遂げられなかったこと、または中断していること」がない状態なので緊張感が弱まり、残業につながってしまいます。
今は「今日はこの仕事とこの仕事」と、複数のタスクに取り組む日が多いですが、それでもすべてのタスクにほどよく手をつけられているわけではありません。これが残業の原因になっている可能性も考えられるので、ツァイガルニク効果を意識して、あえてすべてのタスクに中途半端に手をつけようと思います。
まとめ
なるべく残業したくないわたしにとって、「パーキンソンの法則」「ツァイガルニク効果」という2つの心理効果に出会い、その意味を理解できたことはとても有益でした。
残業が増えると、やっぱり最初に考えるのは「仕事量が多いのではないか?」ということ。もちろん、それが本当の原因である可能性もありますが、すぐに調整するのはなかなか難しく、とくに人手不足が深刻な場合はなおさらです。「いつかは仕事が減る」と待っていてはいつまでも残業が続くだけなので、やっぱり早急に改善を図るならやっぱり自分を見直すしかないかなと思います。
パーキンソンの法則とツァイガルニク効果は、どちらもすぐに取り入れられます。わたし自身、さっそく意識して残業を少しでも減らせたらいいなと思っています。もし同じようなことに悩んでいる人がいれば、ぜひ参考にしてみてください。