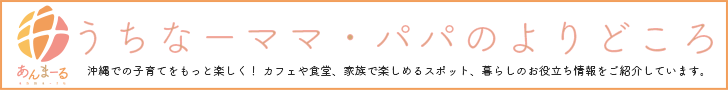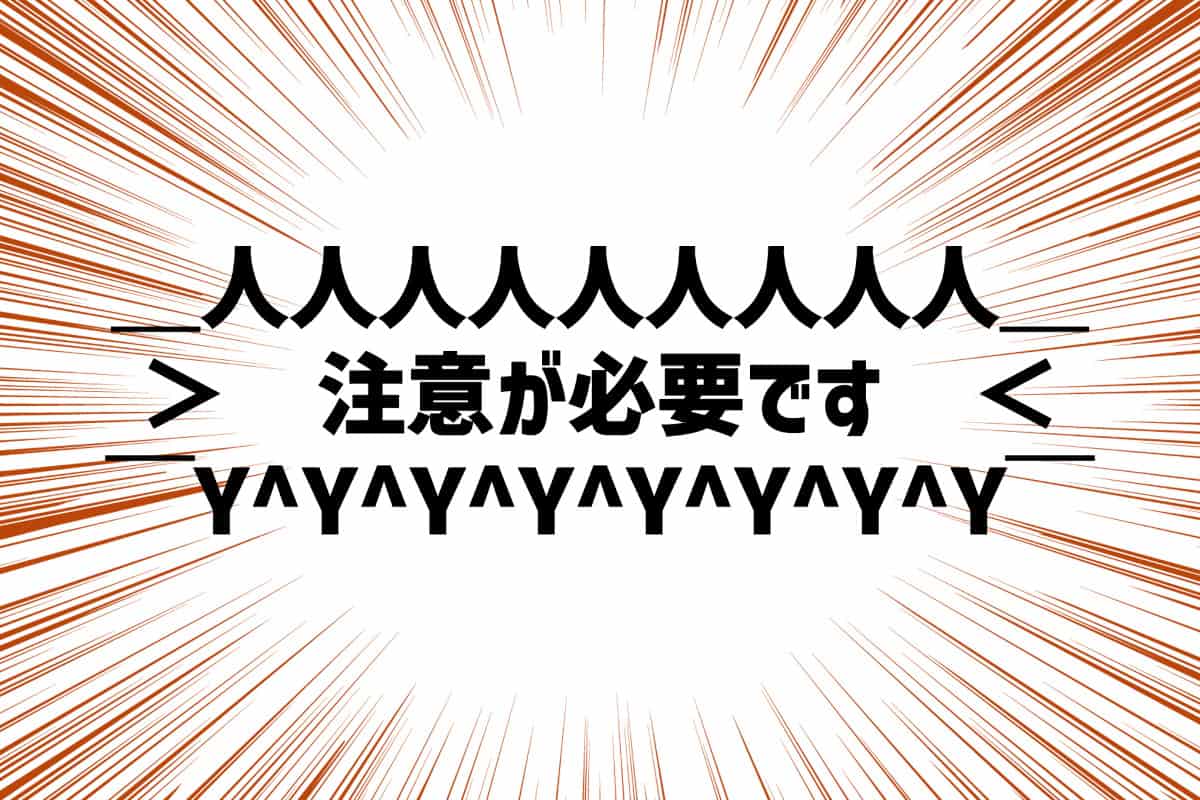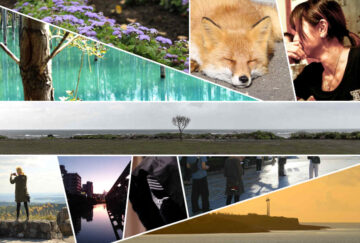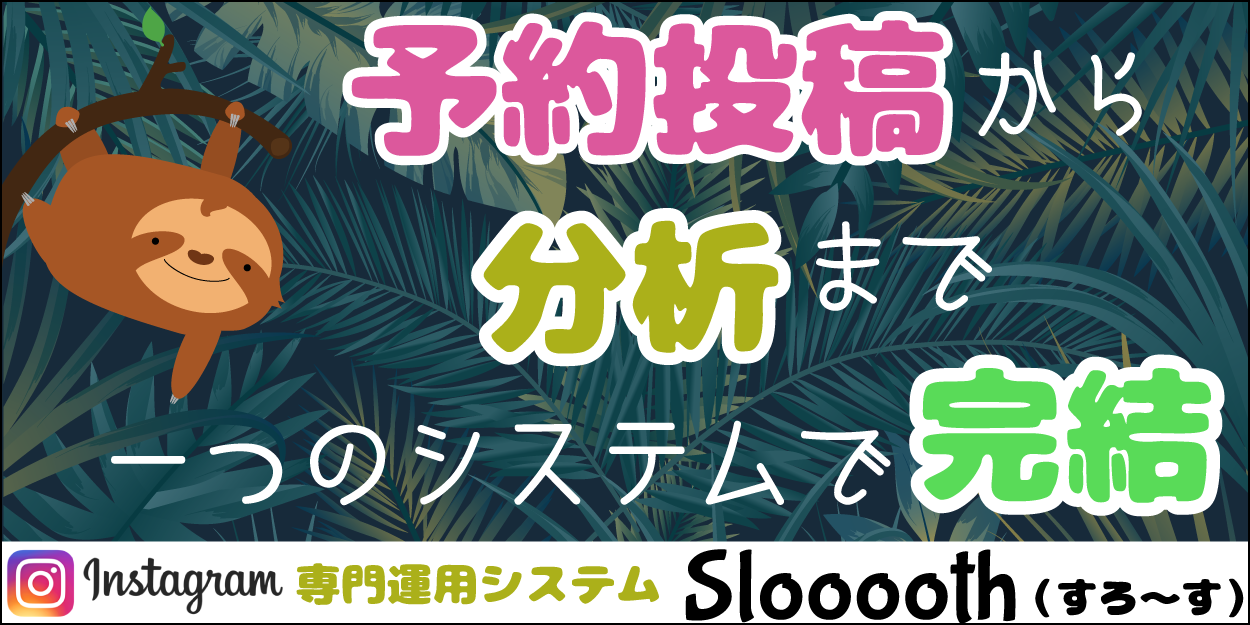カメラ・撮影の仕事を始める人に読んでほしい私の失敗談10連発
失敗談というのは、ときに成功事例よりも価値があるものです。
これからカメラ・写真の仕事を始めるみなさんは、私のたくさんの失敗談を読み、備え、これからのカメラマンライフを幸せに過ごしてほしいと思います。
目次
私がもう経験したくないカメラ・撮影の失敗談
前置きは割愛し、私の失敗談と、どうしたか、どうなったか、どうもならなかったのか、についてどんどんご紹介していきます。
小さいものも入れると実際に100くらい失敗してそうですが、ここでは選りすぐりの10の失敗をピックアップしました。
なお、仕事・プライベートどちらも含みまして、仕事のほうは特定防止のためエピソードをアレンジしています。
SDカードエラーで約1,600枚が吹っ飛ぶ
身の毛がよだつとはまさにこのこと。しかし安心してください、これはプライベートです。
旅行の写真でした。カメラを持ってからの旅行はシャッターを切るのがとにかく楽しく、特に初期は意味もなく撮りまくっていたものです。
カメラ持ち始めはそのくらいがいいですね。たくさん撮ることで学びを得られます。
「なるほど、バックアップしてなかったんだな」と思われたなら、まだまだ。
その前段階、カメラからSDカードを取り出し、カードリーダーでPCに接続し、移動しようとしたらエラーが起きてデータが吹き飛んだのです。
私とて初期の頃からバックアップは心がけていますが、その前に吹き飛ぶとは思いもしませんでした。
なおSDカードは2枚ありましたが、1枚目の約400枚、2枚目の約1,200枚がどちらも吹き飛びました。
1枚目はどうなったか
SDカードって、なんらかのエラーが起きたとき、中のデータを保護するために「緊急避難場所」的なところへ隠す機能があるそうです。
1枚目のSDカードはこの機能が働いていたようで、表では空っぽでしたが、ちゃんとデータが保護されていました。
2枚目はどうなったか
1枚目のデータが無事だったので安心した私でしたが、まさか2枚目も同じように吹き飛ぶとは。
しかも悪いことに、2枚目は保護機能も働いておらず、完全にもぬけの殻状態。間違えてフォーマットしたわけでもありません。
1,200枚が見事に消え失せました。
しかし私は、SDカードを含む記憶メディアは一度記録したデータを完全に消すことはできず、たいていは復旧が可能であることを知っていました。
だからPCやハードディスクを破棄するときは物理的に破壊したほうがいいんですよね。
データ復旧ソフトをインストールし、スキャン。
しかしデータは見つかりません。
たいていのデータ復旧ソフトは無料板で簡単なスキャンを、有料版で本格的なスキャンを行います。
さて、復旧できるかわからないデータのために約1万円を払いましたが、結果、無事に1,200枚を救出できました!
データ移動中にエラーで消失した約1,600枚は、ほぼ無傷で復旧。
なお4枚だけ返ってきませんでしたが、こればかりは両手が上がりましたね。
何が原因だった?
原因を完全に特定することはできませんでしたが、SDカードが2枚とも同時にエラーを起こしたことを考えると、カードリーダーのほうが壊れていた可能性があります。
もちろんカードリーダーはすぐに買い替えましたし、念のため、SDカードも買い替えました。
特にSDカードは消耗品ですから、定期的に買い替える習慣を作っておくのがおすすめです。
データの消失、どうすれば防げる?
変な話、これはプライベートの件でしたので、結局戻ってこなかったとしても私の思い出が消えるだけで済みます。
もし仕事のデータだったらと思うと、それこそ考えたくもない事態です。
バックアップする前のカメラのデータをどう保護するのかというと、一番の対策は「デュアルスロットのカメラを使う」です。
少し前だと、プロ向けの高級機のみの特権でしたが、最近は中級機でもSDカードを2枚挿せる「デュアルスロット」の仕様が増えてきました。
デュアルスロットはなんのためにあるのかというと、撮影した同じデータを両方のSDカードに保存し、1枚になんらかのトラブルがあった場合でももう1枚でリカバリーできるというものです。
これなら、1枚がどうにかなってしまっても、踏みとどまれます。
また、もう1つ、「データをカメラからオンラインストレージへアップロードする」という方法もあります。
各メーカー、カメラからオンラインストレージへ簡単にアップロードできる機能が提供されており、撮ったその場ですぐにバックアップを取ることが可能です。
有線は故障の元。無線で解決できることは、できるだけ無線で済ませたいところです。
仕事の写真が入ったSDカードを草むらに落とす
そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、私もまさか自分がそんなことをするとは思わず、呆然としました。
詳しい状況は少々複雑なので割愛しますが、なぜだかポケットに裸で入れていたSDカードが飛び出して草むらに落ちたのです。
真っ昼間だったものの、どこで落としたのか具体的な場所はわからず。
私はカメラバッグに懐中電灯を常備していますので、これで草むらをかき分け、なんとかSDカードを発見しました。
これはそのとき実際に落としたSDカードです。彼にはたいへん申し訳ないことをしました。
超当たり前だけどSDカードを裸で持ち歩かないこと
カメラに入れた状態か、カードケースに入れるか。
一瞬の距離でも、あんな小さいカード、万が一落としたら行方不明になるし踏み潰す危険もあるので、絶対に裸のままにしてはいけません。
SDカードをすべて置いて撮影へ
これもそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、実際に起きたことです。
なおこれはプライベートです。
車にはすべて載せていたんですが、車で整理しているときにどうもすべてカードケースに仕舞ったらしく、そのカードケースをリュックに入れ忘れてしまったようなのです。
目的地に着いてからSDカードだけ何もないことに気が付き、自分でも何が起きているのか理解できませんでした。
結局そのときは、でっかいカメラリュックに自慢のカメラを2台も入れていながら、スマホで撮るのみ。
仕事じゃなくて本当によかったと思ったものです。
なお普段から、プライベートの予定より仕事のほうが機材チェックはよく見ていますが、これ以降より厳しくチェックするようになりました。
カメラを滝壺にドボン
すべて表題のとおりです。
とにかく乾燥
スマホを含め、カメラ機材を何かしらで水没させてしまった場合、すぐさま心を無にし、以下のことだけを遂行するロボットになります。
- とにかく早く電源を切る
- できるだけ分解する(一眼カメラであれば本体・レンズ・レンズキャップ・バッテリーなど)
- タオルで水気を拭き取る
- 最寄りのスーパーへ走ってジップロックと乾燥剤を買う(乾燥剤は家電量販店でも可)
- ジップロックの中に機材と乾燥剤を入れる
- 2週間放置する
私のカメラはこれで完全復活しました。
おそらく中に浸水していたはずで、よく見るとその跡が見えるのですが、撮影への影響はなし。
それでもどうにもならない場合は、メーカーに送って修理してもらうこともできます。
旅行中にカメラが逝く(3日後に仕事)
滝壺に落ちたカメラと同じカメラです。どっちの事件が先だったか覚えていませんが、なかなかに踏んだり蹴ったり。
明確に落としたとかはなかったと記憶しているんですが、何かの拍子に衝撃を与えていたのでしょう。1分前まで普通に動いていたのに、突然動かなくなりました。
旅行中でしたが、旅行についてはスマホでも撮れます。
でも問題は、表題のとおり、帰ってからすぐ撮影の仕事が入っていたこと。
もう旅行どころではなくなりました。
友人に借りて事なきを得た
私には幸い、こういうときに当てにできる友人がいまして、それでも借りていいものかと悩みましたが、ここは自分が恥を買うべきと思い連絡をしました。
無事カメラを借りることができ、仕事には支障をきたさずに済みました。
なおカメラのほうは、メーカーに送って修理してもらえました。
写真にご満足いただけずクライアント大激怒
今までの失敗談は機材まわりでしたが、これはタイプが変わり、仕事上の失敗になります。
大きめのイベントの撮影で、納品した写真に満足いただけず、親の仇かというくらい怒られました。
ただこれ、私が下手くそだったのかというと決してそういう話ではなく。
イベント公式のカメラマンというわけではなかったので、イベントの邪魔をしないよう、どこまで踏み込んでいいのか現場のディレクターの方に何度も確認をしていたのです。
そのラインを守り、撮影を進めていました。
思えば、クライアントも現場にいたのですが、そのとき私がなぜ前に出ないのか不満そうにはしていました。一応説明もしていたはずです。
そして納品すると、あなたの写真全部遠いじゃないか、どういうことだ、と。
一応やりようはあった
結局どうなったのかというと、大雑把にいえばどうにもなりませんでした。
気持ちとしてはもうお手上げでしたが、やりようはあったかもしれません。
そのとき持っていた私の機材の限界もあって、前に出られなかった結果遠い写真になってしまったのですが、納品するときにトリミングして寄っておけばこうはならなかったなと。
崖下へカメラ落下しかける(レンズキャップは落下)
やはりどうしても、機材の失敗が多いですね。仕事の失敗が多いわけじゃないのは、いいことなのかも。
私は自然を撮るのが好きなのですが、ちょっと危険な場所へ行くこともあります。
そのとき、カメラを崖下へ落としかけまして、カメラは守ったんですがその代わりレンズキャップだけ落ちていきました。
崖下へカメラ落下しかける(レンズキャップは落下)Part.2
と、いうことが2回ありまして。
ちょっと状況は違うものの、崖の上からレンズキャップだけ落ちていったのは同じです。
カメラは死守
状況が崖の上なので、まずは身の安全確保なんですが(この点はちゃんとしていたので大丈夫です)、一般論でいうとカメラ本体は何がなんでも死守したいところ。
何かにぶつけて壊してしまうこと、あるいは、人混みなどで子どもにぶつけて怪我させてしまうことを避けるためですね。
一般には、ストラップで肩から下げればよいですが、これだとブラブラしてわりと注意から逸れがちです。
カメラにはいろいろなグッズがあるので、いろいろ試して自分に合うものを探してみるのがよいですね。
なお私は、「何もつけずに手で持つ」に落ち着きました。
手に持っているほうが常にコントロール下にあって安全なのです。
営業妨害してしまったのか?問題
失敗というと少し違うのですが、苦い記憶が残った件です。
ある店舗の敷地をお借りして取材を行ったことがありました。
もちろん許可をいただいた上でのことでしたが、あとから、お客様へ不便をかけたとしてクレームがきたのです。
具体的な状況への言及は避けますが、確かに「ちょっとうるさくしますので」といった話をした記憶はあるものの、お店の営業に制限をかけるようなことは言った記憶がありません。
とはいえ、店舗側へはうまく伝わらず、店員さんへ過度な配慮を強いてしまったようです。
そのときのクライアントと確認しても、コミュニケーションに瑕疵はなかったとのことで落ち着きましたが、もう少しこちらから配慮できればよかったなと反省しました。
店舗側からすると、取材のスペース貸しなんてそう頻繁にあることではなく、特に店員さんは戸惑うことが多いはず。
曖昧な言い方は避け、スペースなり時間なり、はっきりとゾーニングしてあげるとトラブルにはならなかったかもしれません。
どこかへお邪魔するときは、必要なことは過不足なく伝える!
とても大切なことです。
ISO 12,800ですごくノイジー
カメラについて少し勉強された方であれば、表題が何を示すのか、想像がつくかもしれません。
簡潔に言い表すと、「写真の仕上がりが意図せずに悪くなった」ということです。
ここからは、少し専門的な話として「ISO感度」という設定が登場します。
一から説明していると長くなってしまうため、ひとまずはISO感度について理解している前提で話を進めますが、簡単にだけいえば、「光をキャッチするための感度」です。ISO感度は、上げれば上げるほど光をキャッチして写真が明るくなりますが、そのぶんノイズが乗りやすくなります。
ISO感度の強さによるノイズの差は、以下の画像を見てもらえればわかるでしょう。
撮影においては、可能ならば、ISO感度はあまり上げたくありません。
一瞬を切り取るスポーツ撮影などでは無理でも、静止している被写体を撮るならISO感度を下げることは充分に可能です。
ただ、この案件は、撮るものは静止物ですが、「こっちは勝手に進めておくのでそっちもどんどん撮ってくれ」という感じのもので、けっこう余裕がありませんでした。
そんな中、カメラの設定に脳のリソースを割いている場合ではなく、ほぼオート設定にしていたのです。
その結果、ISO感度が12,800にまで爆上がりしていたのでした。
12,800!
さすがにもうちょっとどうにかできたはず。
なお完全に手持ちで撮影していたのですが、静止物を撮るとき、特に部屋が暗いとき、本当なら三脚は立てたいところ。
もちろん三脚も持っていましたが、いちいちセッティングして撮る余裕もなかったですね。
ただ、そのおかげで撮り漏れはなかったので、そこはよかったかもしれません。
結局写真はどうしたか
ISO 12,800でノイジーとはいっても、実のところ、その写真をスマホの画面で見せるくらいならパッと見ではわかりません。
そのため、失敗かというとそれほどやばい失敗ではないのですが、カメラマンの矜持として仕上がりの悪い状態で渡すわけにはいきません。
たいていの写真編集ソフトには、ノイズリダクション機能がついています。
私が普段使っているAdobe Lightroomにも当然ついているので、その機能でノイズ除去を行いました。
元からいい状態で撮ることが理想ではあるものの、ある程度品質を改善できたかなと思います。
私はこういった失敗もあり、「このくらい除去すれば…」という感覚がけっこう研ぎ澄まされてしまいました。
なお今であれば、AIによるノイズ除去機能が登場しており、ノイズをかなりきれいに除去できます。
私も普段使っていますが、これはすごいです。当時AIノイズ除去があったらなぁと思ってしまいますね。
まとめ:撮影の事故を回避するためのたった1つのポイント
カメラ・撮影におけるたいていの事故は、以下のポイントを守ることですべて防げると学びました。
「仕事用の機材とプライベート用の機材を分ける」
すべて防げるはちょっと言い過ぎましたし、私ができているかというと全然できていないんですが、けっこう大事です。
仕事用のPCや携帯電話は分ける、それと同じこと。
その上で管理をしっかり行えば、機材のミスやトラブルはたいてい防げます。
仕事上のミスは学ぶしかありませんが、このコラムを読んだみなさんはもう私と同じミスはしませんね。
なお仕事用とプライベート用を分けるというのは、フリーランスだとかなり難しいですが、会社所属であればぜひ会社さんが実現してあげてください。
今は小規模でも撮影が可能になるほどカメラ機材が進化していて、ノウハウがなくても参入できるようになっています。
しかしそのとき、従業員の機材頼みで参入しようとすると、事故のもとですし、従業員への多大な負担につながります。
少し話がそれましたが、改めて失敗談をまとめてみると、恥ずかしいエピソードもけっこう出てきました。
今回は失敗談なので、自分のミスが絡むエピソードだけを集めましたが、「撮影に関する事故」にまで広げるとまだまだいろんなエピソードが出てきます。
もしかしたら、またこちらのコラムで披露することがあるかもしれません。