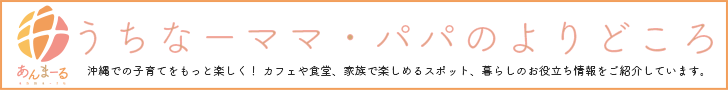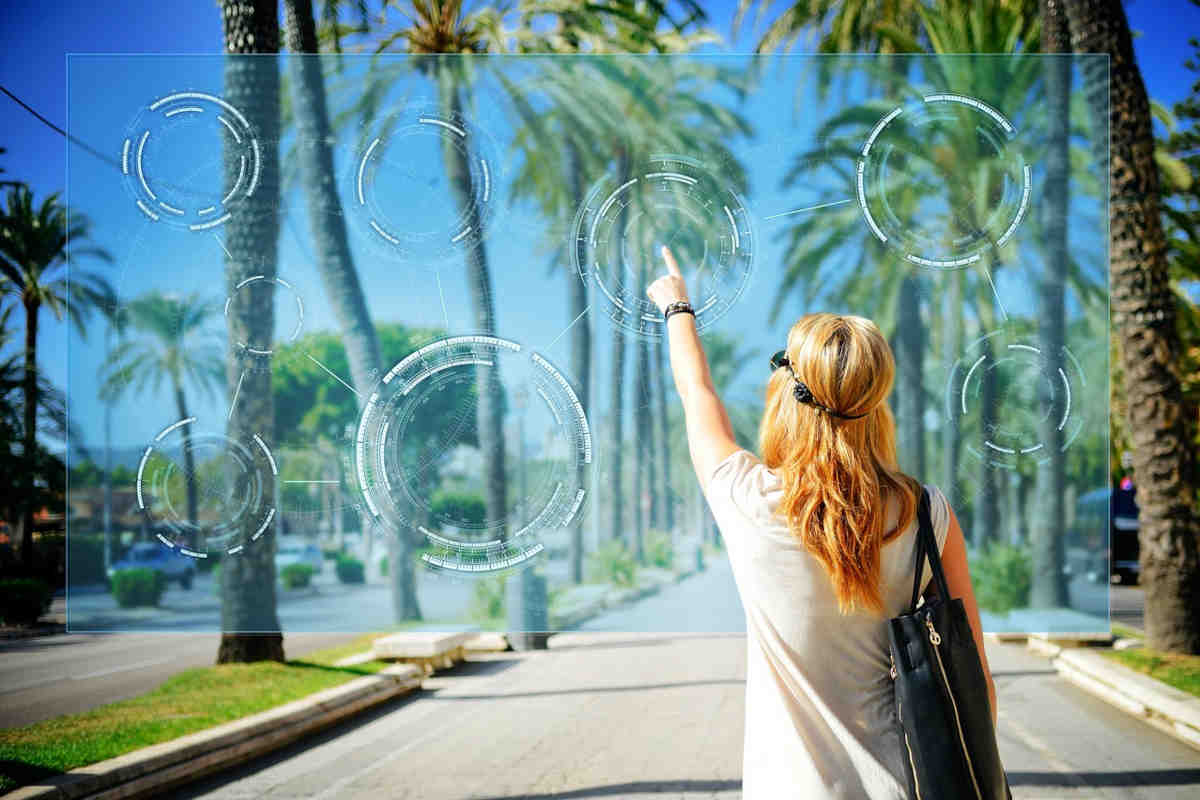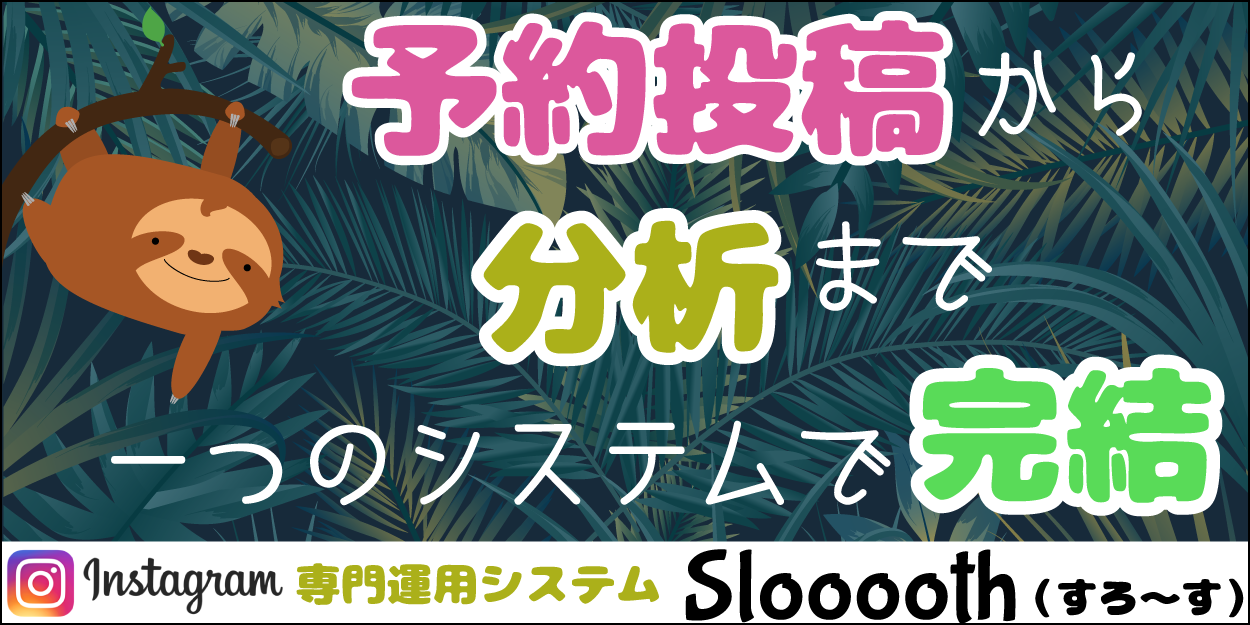ChatGPTの解説記事を作成するためにChatGPTを駆使した話
こんにちは、よしてるです。
この間、友人と居酒屋で飲んでいるときに、面白がってChatGPTにおすすめの日本酒を教えてもらいました。すでに飲み比べセットで3種の日本酒を飲んでいましたので、その3つをChatGPTに教え、残り3つのラインナップから次のおすすめを聞いてみたのです。そうしたら、おすすめしてもらった次の日本酒がとても美味しくて、びっくりしました。
他の日本酒が選ばれていたとしても似たような感想になっただろうとは思いますが、ChatGPT、ひいては生成AIには無限の可能性があるなと感じたエピソードです。
さて、そんな私に、ChatGPTの解説記事を書く機会がありました。初心者的な内容であれば、そんなに難しいことはないのですが、専門的に少し突っ込んだ内容が求められていたため、「これはChatGPTに頼ろう」とすぐに決めました。
なお、結果として、ChatGPTの回答テキストから記事内に使用したものはゼロでした。
目次
ChatGPTは記事作成に使えるのか?
ChatGPT、ひいては生成AIは記事作成に使えるのかどうか、これはAI時代において常に投げかけていきたい命題ですね。
なお、本ブログには他にyurika gimaによるコラム「Chat GPTで記事作成はできる?基本的な使い方と絶対に押さえておくべき注意点」がありますので、こちらもあわせてご覧ください。
私の結論としては、「現段階ではライターの代わりにはなりえない」となります。現段階とは、ChatGPTでいえば「GPT-4o」までの段階を指し、私は「o1-preview」はまだ使っていません。
ただし、今後の進化によってはどうなるかわかりません。AIの進化にはワクワクもあり、怖いものもありますね。
「ライターの代わりにはなりえない」とは、生成AIを駆使して書いた記事は、駆使したライターのそもそもの能力を超えることは難しい、という意味です。ライタースキルがない人が生成AIを使って記事を書いても、一見整った内容にはなっても、「使える記事」になるかは怪しいでしょう。
ただし、ライターが自身の100%を出すための「スピード」を一気に速くすることができます。「図書館」で調べるより「Google」で調べるほうが速いように、「Google」より「ChatGPT」のほうが速い、というイメージですね。
余談:Googleはそもそも使い物にならない
ちょっとセンセーショナルな見出しをつけましたが、少しインターネット老人的な余談をご容赦ください。
生成AI登場よりずっと前から、調べ物をするのにGoogleは使えなくなってしまった、と言われることがあります。これは、誰でも簡単に、どんな企業でも気軽に記事を作成して検索結果に載せられるようになった結果、本当に有用な記事は上がってこなくなった、という意味です。
私の感覚で話させてもらうと、2000年代のインターネットは濃い知識の宝庫でした。調べたいと思ったことを深くまで知ることができましたし、情報がそれほど整理されていないことから、情報の真偽について自身で判断することも難しくありませんでした。
今は、専門家が書いたとは到底思えない浅いコタツ記事が溢れかえり、Google検索結果の上位を独占しています。知りたいことの表面しか知れないどころか、変に整理されているせいで真偽もよくわからず、リライトばかりでどこに一次情報があるのかさっぱりわかりません。
なお、私自身もそんなコタツ記事ライターであることを一応申し添えておきます。
最近では、生成AIの登場によりGoogleの牙城が崩れるとか、もはや不要になったとか、言われるようになりましたが、もうずいぶん前からGoogleは使い物にならなくなっています。
と、ここまで強い論調で述べてしまいましたが、ツールは使いようです。こうは言うものの私はそこそこのGoogleユーザーであり、検索結果の上位に求める答えがないことを理解しつつ、調べ物に活用しています。
さて、ChatGPTの話に戻りますが、もちろん完全なツールだとは到底言えないものの、「調べ物」においては検索エンジンを大きく上回るツールであることは間違いなさそうです。
ChatGPTの解説記事のためにどうChatGPTを使ったのか
私はこのChatGPTの解説記事を書くまで、ChatGPTをがっつり使ったことはありませんでした。なんだかんだ、Googleでだいたい事足りたからです。あんなにこき下ろしておいてなんですが。
それなのにChatGPTの解説記事でChatGPTを使おうと思ったのは、内容が専門的な領域にまで突っ込むものであり、AIについてはニュース程度の知識しかない私には荷が重いと思ったためです。
まずはChatGPTに教えてもらう
ChatGPTを使っていて一番いいと思ったポイントは、Googleの検索で上位にヒットするどんな記事よりもわかりやすいところでした。
技術の革新を喜ぶべきか、人類の無能さを嘆くべきか。
私が書くものもふくめ、検索結果の上位を目指す記事はChatGPTに到底勝てません。ChatGPTを使えば使うほど自分が情けなくなってくるのですが、こと調べ物においては本当に有用でした。
私が実践して「使える」と思ったのは、以下2つの使い方です。
全体について聞いてから詳細について聞く
特に専門的な内容について知りたいとき、自分が何について知らないのかもわからないものです。なので、まずは全体について聞いてみます。
すでにChatGPTの回答はわかりやすいので、運がよければこの時点でいい感じの理解を得られます。ただ、そう簡単にはいきません。ChatGPTは回答の中で専門用語を平気で使ってきますので、わからない用語や、理解できなかった部分についてさらに質問を重ねます。
こうすると、その内容について十分な理解を得ることができます。このスピードは、Googleで上位記事を読み漁るよりも爆速です。
素人向けにしたり専門家向けにしたりする
これは面白いと思ったのは、読者レベルを指定して質問することでした。
「◯◯について教えてください」と質問するだけだと、内容はわかりやすいものの、想定する読者レベルはふんわり平均的です。専門的な内容を知りたい場合は、けっこう意味不明なことが多いでしょう。
そこで、「初心者向けに説明してください」と質問をすると、どういう仕組みなのか、本当に初心者向けに噛み砕いて説明してくれます。これにはライターとしての自信を喪失しました。こんなにわかりやすく説明してもらっては、人間のライターは本当にいらないんじゃないかと思わされてしまいます。
そこでさらに、「改めて専門的な説明をお願いします」と質問をすると、最初の回答と同じ内容が返ってくるかと思いきや、初心者向けに噛み砕いた内容をベースにしつつ専門用語を加えて説明してくれます。
この三段活用により、私の「調べ物」は爆速で深いレベルにまで到達しました。Googleで検索結果の下位まで漁ったりキーワードを変えたりしても同じ結果には到達できるでしょうが、どれだけ時間がかかるかはわかりません。
次にGoogleで調べる
Googleについてちょっとボロクソに言ってしまいましたが、ツールは使いよう。生成AI時代において、検索エンジンは「生成AIの後に使う」のがかなりよさげです。
私はChatGPTの専門的な内容についてChatGPTに教えてもらったあと、その答え合わせをGoogleで行いました。生成AIは必ずしも正しい情報を返してくれるわけではないので、真偽については調べる必要がある…生成AI活用の常識ですね。
なお、本当にChatGPTは平気で嘘をつきます。
ChatGPT自身のことなのに、これは間違いです。「GPT-4o」の「o」は「omni」を意味すると、公式サイトに書いてあります。
うっかりするとこういう罠に簡単に引っかかってしまうので、注意が必要ですね。
ChatGPTによってその内容の理解が深まっているので、Google検索でもどのように調べれば求める答えが出てくるのか、直感的にわかります。
しかも、専門的な内容を解説している記事に出会っても、その内容が理解できます。ちょっと自分でも驚きました。普通にたどり着いただけなら、絶対にちんぷんかんぷんだったはずが、ChatGPTで下調べすることで頭に入ってくるのです。
一応構成も作らせてみる
ChatGPTの解説記事を書くために必要な知識を脳みそに詰め込んだところで、記事作成に入っていきます。
生成AIの活用として、構成(アウトライン)をAIに作らせる、というのは定番といえば定番でしょうか。そのまま使うのではなく、必ずライター視点によるチェックを入れる前提で、構成を作らせるのはアリかもしれません。
ただ、私もChatGPTに構成を作らせてみたのですが、ちょっとこれはそのまま使うには不十分なものでした。というのも、記事作成にはペルソナ(ターゲット)があります。記事を読んで欲しいターゲットに理解してもらうことを考えると、ChatGPTの作る構成は平均的すぎて、「使える記事」になるかどうかわかりません。
ターゲットについての情報をChatGPTに伝えたり、あるいは記事作成やマーケティングに特化したChatGPTベースのAIライティングツールを使ったりすればまた違ったかもしれませんが、私の肌感としては「そのまま使える」レベルが出てくるのは現時点では難しいだろうと思います。
なので、ChatGPTが作ってくれた構成をベースに、これをブラッシュアップします。
構成をイチから考えてもいいのですが、叩き台があるのとないのとでは作業スピードに違いがあります。そういう意味では、ChatGPTに構成を作らせるのはアリでしょう。
なお私が作った解説記事は、最初にChatGPTに出してもらった構成からはけっこうかけ離れました。叩き台にすることで作業スピードは速くなったものの、ここはまだまだ人間のライターの領分です。
念のため、本文も書かせてみる
せっかく一気に何千文字も出力できる生成AIツールを使っているので、本文も書かせてみたいですよね。極論をいえば、それで素晴らしい記事が出来上がるならそのまま使えばいいのです。
ただ、冒頭でも述べたとおり、私の解説記事ではChatGPTの回答テキストからコピペして使う部分はひとつもありませんでした。想定するターゲットや、掲載メディアの特性、クライアントから求められているクオリティ、文章のクセ、普段自分が書いているテイストとのギャップなどなど、ChatGPTの作る記事は細かい乖離が多くてかゆいところに手が届きません。
なお、この他の記事作成においてもChatGPTを大なり小なり活用していますが、私の肌感として、ChatGPTに記事を書かせて「そのまま使えるぞ!」と思ったら、ライターとして仕事をするための最低限のスキルも身についていないかもと危惧する必要がありそうです。今後のAIの進化によっては、どうなるかわかりませんが。
ChatGPTも使いよう
Googleは使いようですが、ChatGPTも使いようです。ツールというのは結局、上手く使える人がいい結果を引き寄せられるんだなぁと、生成AIの登場によって改めて考えさせられます。
なお、本記事でご紹介した「ChatGPTでまず調べる」→「Googleで調べる」という活用方法はけっこうおすすめなのですが、これは生成AIの中でもChatGPTがぴったりです。Google GeminiやPerplexity、ChatGPTベースのCopilotは、回答内容にネット上からソースを出してくれるので便利なのですが、これは「自分で調べる」力を削いでしまうように感じています。ソースを出してくれたところで、回答内容が正しいかどうかは自分で調べるまでわからないので、テキストのみを返すChatGPTのほうがライタースキルを磨きつつ活用できるはずです。