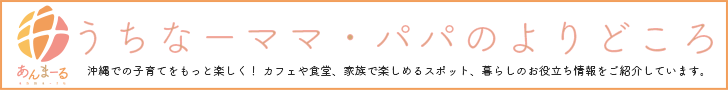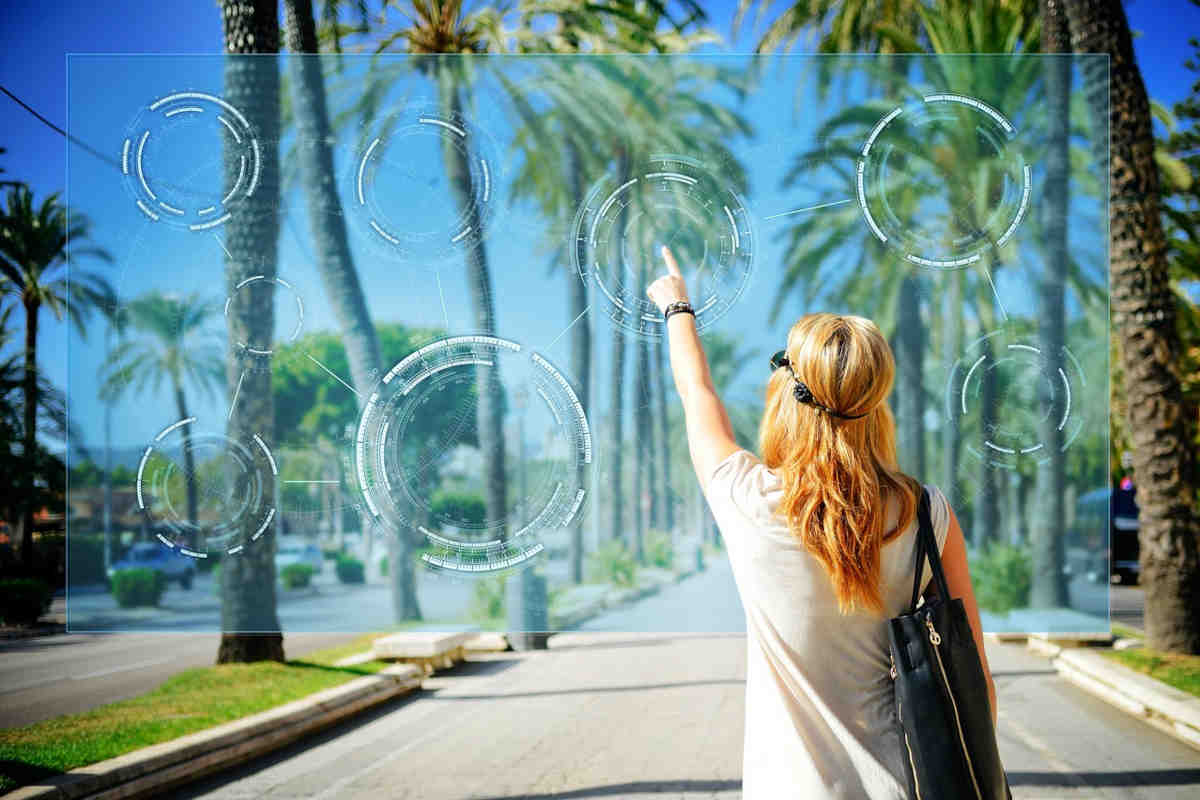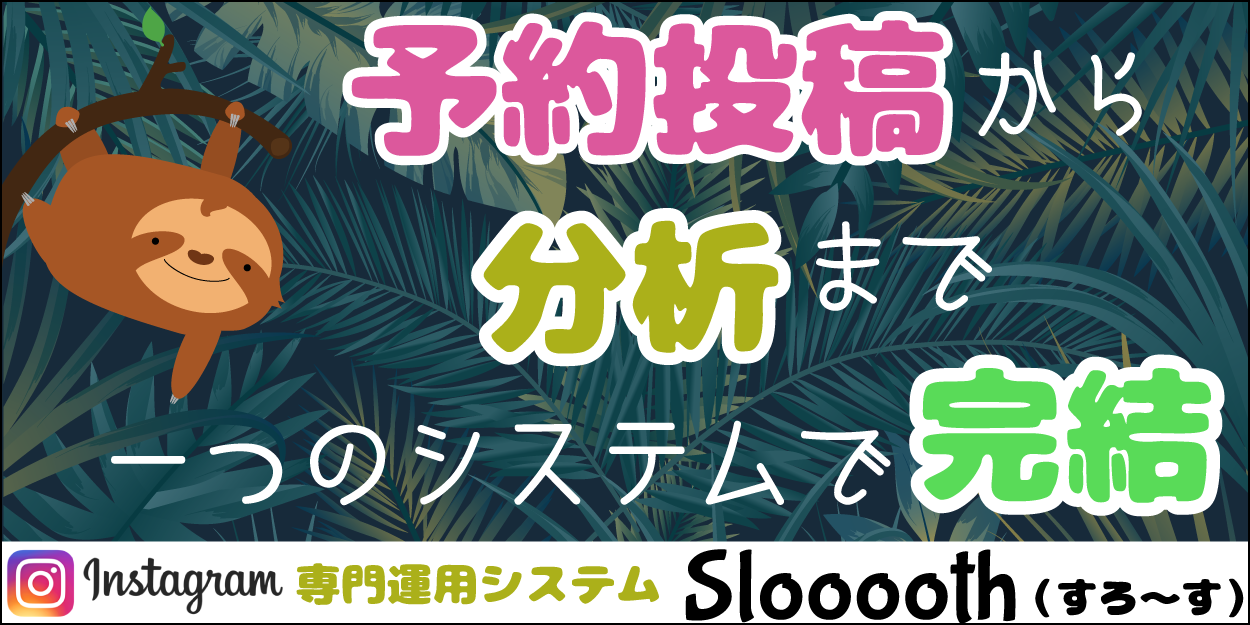優秀な採用担当者になるために。ちょっぴり辛口な心得3選
皆さん、こんにちは! LOVELETTER WORKS 株式会社の篠原です。
10/1に内定式が終わり、内定者の皆さんの元気な姿を見て、ホッと胸をなでおろしている採用担当者の方も多いのではないでしょうか? 採用活動って、なかなかゴールが見えづらい仕事ですよね。 だからこそ、一区切りついたこのタイミングで、日頃自分がどんなことを考えながら仕事をしているのか、改めて振り返ってみるのも良いかもしれません。
今日は、私が8年間新卒採用担当として経験してきた中で「これは大事だな」と感じた、採用担当者としての心得を3つまとめてみました。
人と対峙し、その人の人生を左右するかもしれない仕事だからこそ、自分への戒めも込めて、今回はちょっぴり辛口モードでまとめています。 人事の方も、現場の社員さんも、採用に関わる全ての方に、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
自分の判断に自信を持つな!常に疑え!
面接を数多くこなしていると、誰しも自分なりの選考基準や、人を見極める際のコツのようなものが身についてくるものです。 特に経験豊富なベテランともなると、「挨拶の仕方で大体分かる」「無人島に持っていくもの一つで人柄が分かる」といった、一見根拠が乏しい独自の理論を編み出し、人を見る目に自信を持つ方もいらっしゃいます。
確かに、いわゆる「長年の勘」というものはあるかもしれません。数多くの面接を通して経験を積み重ねる中で、ある程度の傾向やパターンが見えてくることもあるでしょう。 しかし、決して忘れてはならないのは、「人は一人ひとり全く異なる」ということ。
人は、「分からない」という状態に不安を感じやすいものです。だからこそ、つい他人を型にはめて「分かったつもり」になりたくなるのかもしれません。けれど、過去の経験という、自分だけの物差しにはめて判断をしてしまうことに慣れると、その型にはまらない、可能性を秘めた人材を見逃してしまうリスクがあります。
私自身、採用担当として2~3年経験し、何百名もの学生さんとお会いする中で、ある種の「パターン認識」ができるようになりました。 「こういう経験をしている学生は、こういう仕事に興味を持ちやすい」といった傾向が見えてくると、それが自分の成長だと勘違いしていた時期もありました。
しかし、ある時ふと、「私は目の前の学生を本当に理解しようとしているのだろうか?それとも、ただパターンに当てはめて安心したいだけなのではないか?」と自問自答するようになりました。
そこから、過去の経験や先入観に頼らず、「分からないからこそ、もっと知りたい」という探究心を持って、目の前の人間と誠実に向き合うことの大切さを改めて実感しました。思考停止せず、「自分の判断が常に正しいわけではない」と謙虚な姿勢を持ち続けることで、人を見る目を養うことができます。
常に自分自身の判断を疑うのは、成功体験が積みづらく常に不安な気持ちにもなりますが、採用担当者は不安なくらいがちょうどいい!その不安が「もっと相手を知りたい」という気持ちに繋がり、会社にとってかけがえのない出会いをもたらす可能性を秘めていると信じています。
口説くことを恐れるな!自分が良いと思うことは、胸を張って語れ!
日本には「謙遜の美徳」という言葉がありますが、採用活動においては、自社や自分の仕事の良さをアピールすることにためらいを感じてしまう方もいるかもしれません。 「口説く」という言葉自体に抵抗感を示す方もいらっしゃるでしょう。 事実を伝えて相手に判断を委ねることも大切ですが、それは同時に、自社の魅力を最大限に伝え、責任を持って候補者と向き合うことから一歩引いてしまっている状態とも言えるのではないでしょうか。
口説くことに対してネガティブな印象を持つことは、相手には自社を理解し、選択する能力がないと決めつけているのと同じです。 また、事実を伝えるだけでは、この競争の激しい採用市場において、優秀な人材を獲得することは困難です。
採用担当者として、一緒に働きたいと感じた人材には、ぜひあなたの情熱を惜しみなく注ぎ込んで口説いてみましょう。 自分の言葉で率直に思いを伝え、自社の魅力を語ることは、決して恥ずべきことではありません。 口説くということは、ただ良いことばかりを並べ立てることではなく、時には課題や改善点も共有し、本音で語り合うことで、候補者とより深い信頼関係を築くことにもつながります。
「どうすれば口説けるのか分からない」という方は、もしかしたら自社のことをまだ十分に理解できていないのかもしれません。
私が以前働いていた会社は、従業員数1000名以上と大規模で、様々な部署やチームがありました。 だからこそ、職種や役職、年代など、立場によって感じる会社の魅力も実に様々だったんです。 そこで、積極的に社員とコミュニケーションを取り、自社の良い点も悪い点も含めて率直な意見を聞いてみることにしました。すると、驚くほど多様な視点から自社の魅力を再発見することができたのです。
様々な社員の声に耳を傾けることで、自分一人では気づくことのできなかった自社の魅力を再発見することができ、それを自分の言葉で語る練習を重ねることで、次第に自信を持って候補者へ想いを伝えられるようになったんです。
自分の言葉で会社の想いを伝えて、候補者と真剣に向き合った結果、入社を決めてくれた瞬間は、採用担当として一番やりがいを感じる瞬間でもありますよね! ぜひ、この喜びを体感するためにも、胸を張って口説いていきましょう!
経験値の低さは、視野の狭さ! 新しい体験から自分自身を磨け!
採用担当者は、日々多種多様なバックグラウンドや能力・スキルを持つ方々と出会います。 時には、自分には全く知識のない分野を得意とする方や、自分には経験のないことがその方の価値観や行動に大きな影響を与えている場合もあります。
そんな時、自分の理解を超えているからといって、その方を「分からない」と切り捨ててしまうのは、採用担当者として非常に勿体ないことです。 むしろ、採用担当者だからこそ、できる限り相手の立場に立って理解し、共感しようと努めることが大切です。
そのためには、日々の生活の中でも、積極的に新しいことに挑戦し、自分自身の経験の幅を広げていくことが重要となります。
私自身も、「初めてのことは多少無理してでもやってみる」という気持ちで、日常に初めての体験を増やすようにしてきました。 また、小説や映画、ドキュメンタリーなどを通して、自分とは異なる環境で生きてきた人々の価値観に触れることも意識的に行ってきました。
こうした経験を通じて、自分自身の視野が広がり、多様な価値観を受け入れる柔軟性が身についたと感じています。 そして、それは採用活動においても、目の前の候補者をより深く理解し、その方の可能性を最大限に引き出すことにつながっているはずです。
「食わず嫌い」という言葉があるように、人は未知のものに対して、つい身構えてしまいがちです。 しかし、一歩踏み出して飛び込んでみれば、そこには新しい発見や感動が待っているかもしれません。 採用担当者として、そして人間として成長し続けるためにも、ぜひ、日々の生活の中で「初めての体験」を積極的に増やしていきましょう。
「採用」という仕事に慣れないことが、優秀な採用担当者への道
以上が、私の採用担当者としての心得です。 これら3つに共通するのは、「自分の物差しで測らない。最大限自分の物差しを広げる」ということです。
私が考える、どこでも重宝される優秀な採用担当者とは、会社の様々な人材ニーズに応えられる人、つまり、様々なタイプの人材を採用できる人です。創業期と安定期では、企業が求める人材像は異なります。 また、変化の激しい現代社会において、いつ求める人材像が変わるかも分かりません。 企業が継続的に成長していくためには、多様な人材が必要となります。
どのような状況でも、多様な人材を採用できるようになるためには、採用担当者自身が自分の物差しを最大限広げ、口説き、判断できるようになることが重要です。
また、個人的には、採用担当者は人間的にも面白く尊敬される人であってほしいと思います。そのためには、自分自身を律することが大事だと思っています。
採用担当の仕事の一つは「人を判断する」ことですが、日常生活では、人を判断する行為はあまり良いこととはされていませんよね? 人を判断することに慣れてしまうと、驕りや慢心が出て視野が狭くなり、まるで自社の採用基準が絶対であるかのように感じてしまうこともあるのです。
だからこそ、いつまでも「採用」という仕事に慣れずに、フレッシュな気持ちで候補者に向き合うことを大切にしています。
今回は少し辛口で心得をまとめてみましたが、日々、自分の判断軸を疑い、柔軟でしなやかな物差しを身につけ、変化に対応できる採用担当者を目指していきましょう!