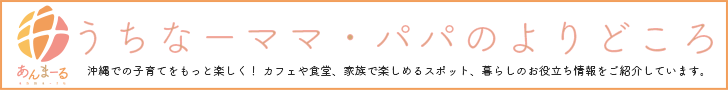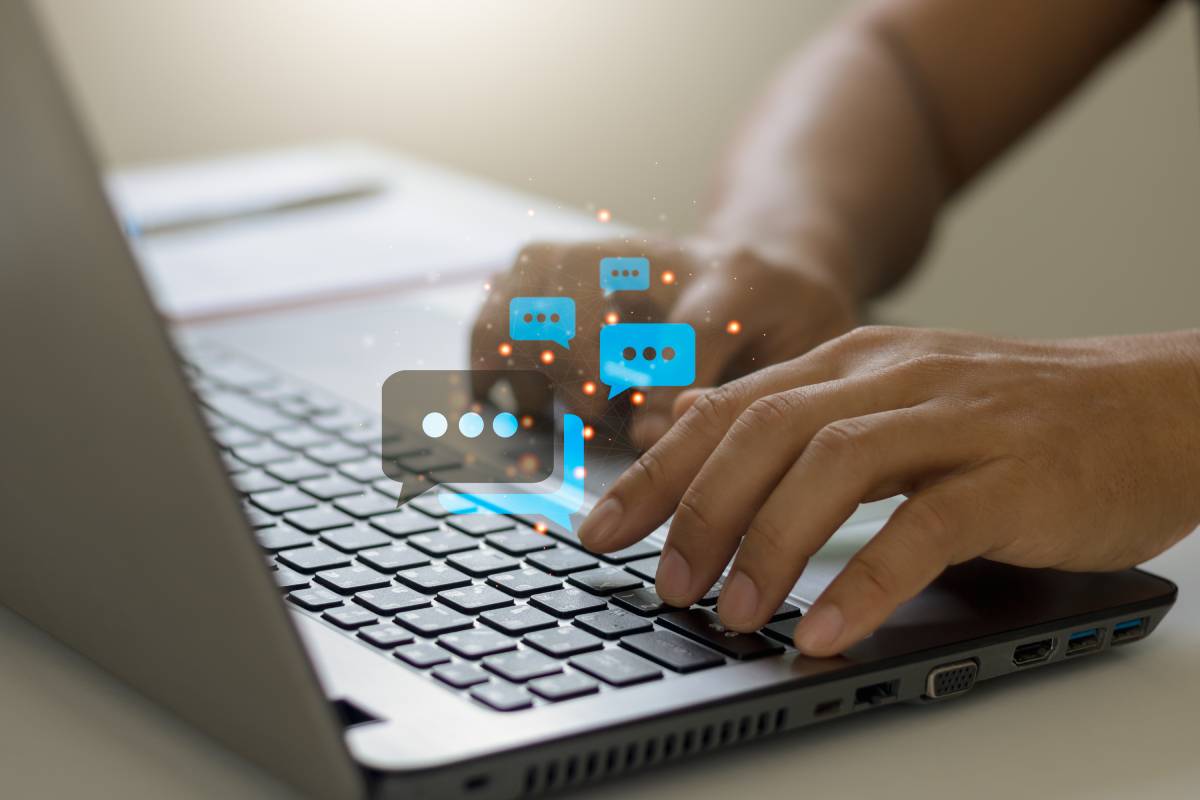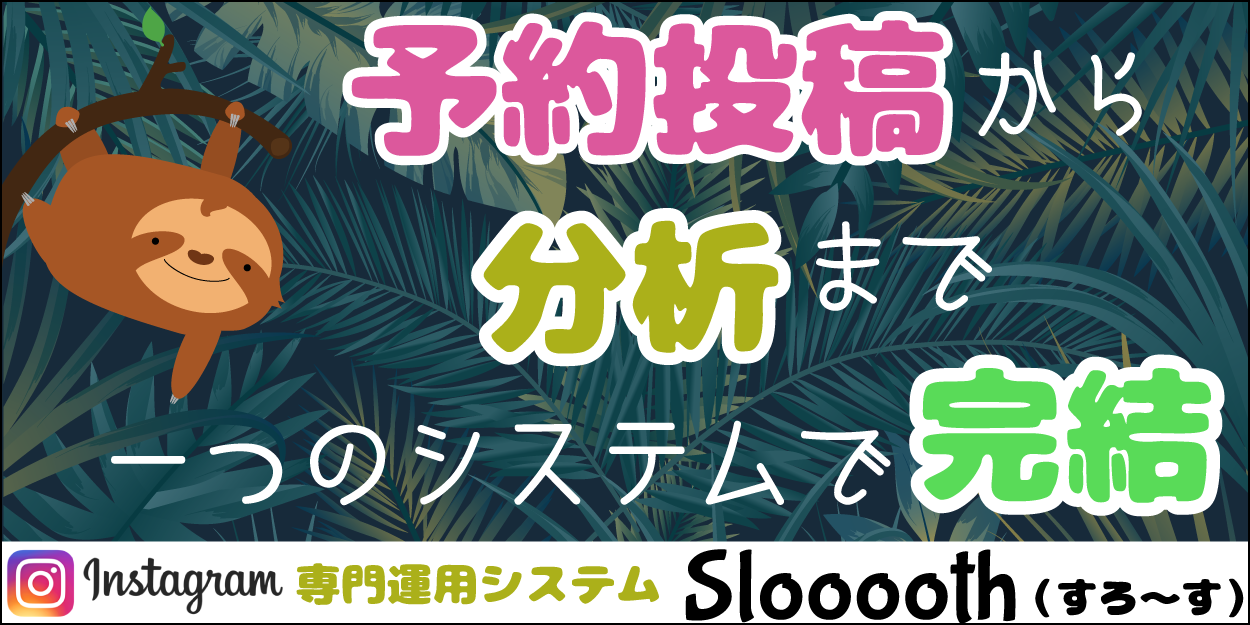成長は「足し算」だけじゃない!「当たり前」を極める重要性
みなさん、こんにちは。LOVELETTER WORKS 株式会社の篠原です!
先日、新卒採用面接で就活生から「ビジネスパーソンとして成長するために必要なことは何ですか?」という質問を受けました。
この質問をきっかけに、改めて「成長」について考えてみたんです。
「成長」って、よく使う言葉ですよね。でも、人によって定義が違ったり、年齢によって意味合いが変わってきたりしませんか? 20代の頃と30代の今で、私自身、成長に対する考え方も変化してきました。
ビジネスの世界では、「成長」は避けて通れないもの。でも、「成長しなきゃ」って思うと、なんだかプレッシャーを感じたり、頑張っているのに実感を得られなかったり……と、モヤモヤを抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、社会人11年目の私が考える「成長」についてお話ししたいと思います。肩の力を抜いて、一緒に考えてみましょう。
目次
成長=スキルアップ?それだけじゃない成長の形
では、そもそも「成長」って何でしょう?
辞書を引くと、「成長」は「現状よりも能力や成果が向上すること」と定義されています。能力の向上というと、新しい知識やスキルを身につける、経験を積むといったことがイメージしやすいですよね。成果の向上は、売上アップや顧客満足度の向上、業務の効率化などが挙げられます。
でも、「成長=新しいスキル習得」とか「成長=資格取得」といったイメージだけが先行してしまうと、少し息苦しく感じませんか? 実は、もっと身近なところに成長の種は転がっているんです。
例えば、いつもは3時間かかっていた資料作成を、2時間で終わらせることができたら? 昨日よりもお客様への対応がスムーズにできたら? これも立派な成長です。
若手の頃は、右も左も分からない状態です。当時の私は、新しい知識やスキルを吸収して、自分自身にどんどん「足し算」していくイメージで成長を捉えていました。
しかし、経験を積む中で、成長とは単に新しいものを取り入れるだけでなく、今ある自分の力を「昨日より今日、今日より明日」と少しずつでも磨き上げていくことだと感じるようになりました。言い換えると、「基礎を徹底し、当たり前のレベルを上げる」ということになります。
失敗から学んだ成長の目的
「基礎を徹底し、当たり前のレベルを上げる」こそが成長の本質だと考えるようになったきっかけは、入社4年目で初めて大きな採用イベントの企画責任者を任された時の経験でした。
裁量の大きい仕事にワクワクしながら、プロジェクトマネジメントの本を読み漁ったり、他社のイベントをリサーチしたりと、意気揚々と準備を進めていました。しかし、いざプロジェクトがスタートすると、トラブルの連続。スケジュール管理の甘さからコンテンツがギリギリまで完成せず、チーム内のコミュニケーション不足で認識のズレが頻発し、焦りと業務過多でチームの雰囲気も悪化……。今思い出しても胃が痛くなるような日々でした。
「私には何が足りないんだろう……」と悩み、ビジネス系のブログを読み漁ったり、スケジュール管理ツールを導入したりと、とにかく「自分がうまくやれるように」と必死にもがいていました。
そんな時、上司から言われた言葉が、私の心に深く突き刺さりました。
「うまくやろうとしなくていいから、メンバーから『この人に協力したい』と思われるような責任者になりなさい」
当時の私には、まさに目から鱗が落ちる思いでした。それまで私は、「プロジェクトを(自分が)うまく回せるように」と、自分だけの成長ばかりを考えていたのです。
しかし、ビジネスは必ず相手がいて、その相手を満足させることがゴールです。つまり、成長の先には必ず「相手のハッピー」が必要なのだと気付かされました。
もちろん、自分自身が成長を実感できることは、仕事へのモチベーションを維持する上で大切です。しかし、その前提にあるのは、「相手から信頼を得るための成長」「相手に満足してもらうための成長」なのではないでしょうか。
この経験から、私は「相手がこの人だったら協力したい、信頼できる」と思ってもらうために必要なことを真剣に考えるようになりました。そして、新しい知識やスキルももちろん大切ですが、それ以上に、自分の得意分野や相手が自分に期待している領域について、徹底的に力を発揮することこそが重要なのではないかと思うようになったんです。
当たり前を徹底的に
そこから、私は「相手に信頼されるために、今自分にできることは何か?」を徹底的に考え、行動に移しました。具体的には、
- プロジェクト進捗状況の情報共有を毎日行う
- 質問や相談には、回答するだけでなく、+αの提案を行う
- 連絡には即レス
- 納期のリマインドを3日前と前日に行う
- 困ったことはその日中にメンバーに相談する
- Good Jobを見つけて、1日1回全体チャットに共有する
- 感謝の気持ちを言葉で表す
などです。
こうやって書き出してみると、どれもごく基本的なことばかりですよね。でも、忙しい日々の中で、これらを徹底して実践するのは意外と難しいものです。
しかし、こうした「基礎を徹底し、当たり前のレベルを上げる」を意識し続けた結果、メンバーは私に徐々に安心感を持ってくれるようになり、チームワークが向上しました。そして最終的には、参加者にも満足してもらえるイベントを開催することができたんです。
この経験を通して、私は「ビジネスにおいて求められる成長とは、当たり前のレベルを上げること」だと確信しました。派手なスキルや知識を身につけることだけが成長ではありません。むしろ、誰もが「できて当然」と思っていることを、誰よりも高いレベルで実践できるようになることこそが、真の成長であり、信頼を勝ち取るための鍵なのではないでしょうか。
無意識にできることが強みになる
私の実体験から、基礎を徹底し、当たり前のレベルを上げることが成長の本質であることをお伝えしてきましたが、ビジネスにおいて競合よりも優位になるという点でも、当たり前のレベルを上げることはとても重要です。
人が何かを学ぶ時、5つの成長のステップを踏むと言われています。
- ①無意識的無能: 知らないし、できない
- ②意識的無能: 知っているが、できない
- ③意識的有能: 意識すればできる
- ④無意識的有能: 無意識にできる
- ⑤意識有能/無意識有能:人に教えることができる
ビジネスにおいて、成果につながるのは、④無意識的有能( 無意識にできる)と⑤意識有能/無意識有能(人に教えることができる)ですよね。
成果を出す上では、①や②はできない時点でそもそも話になりませんし、③は意識することが求められるので、他の人と比べて時間や労力がかかってしまう可能性が高いです。
また、大抵の情報はネットに転がっているからこそ、月並みの知識やスキルは誰でも得られてしまいますよね。
だからこそ、無意識にできること、人に教えることができるレベルまで自分の中に落とし込まれている状態にする必要があります。
たしかに新しいことを知っていることは大事だし、色々なことができるスキルも大事ですが、それ以前にまずはすでにできていることを磨き上げ、無意識でできること=当たり前のレベルを上げることで、競合に差をつけることもできるはずです。
成長は「当たり前」の底上げから:マインドセットを変え、無意識レベルの成長を目指そう
ここまで、成長の定義や目的、そして基礎を徹底し当たり前のレベルを上げることの重要性についてお話ししてきましたが、これは知識やスキルに限った話ではありません。私たちの仕事に対するマインドセットにおいても、同じことが言えるのではないでしょうか。
例えば、「ミスなく納品物を完成させること」を目標とする人と、「ミスなく納品物を完成させるのは当たり前で、次回受注に向けた提案をセットで考えること」を目標とする人では、成果物のクオリティに雲泥の差が生まれるはずです。
自分の中の「当たり前」のレベルを引き上げることは、最初は大変かもしれません。しかし、一度そのレベルに到達すれば、それは文字通り「当たり前」となり、無意識のうちにできるようになります。すると、自分では特に努力したつもりはないのに、クライアントから高い評価を受ける、なんてことも起こり得るのです。
もしあなたが、「頑張っているのに成長を感じられない…」と悩んでいるなら、ぜひ1年前と比べて、自分の中の「当たり前」のレベルがどう変化したかを振り返ってみてください。きっと、あなたが気づいていないだけで、たくさんの成長があるはずです。
成長とは、派手な成果や目に見える結果だけではありません。日々の小さな積み重ね、そして自分の中の「当たり前」を少しずつ底上げしていくことこそが、真の成長であり、ビジネスパーソンとしての価値を高めるための確実な一歩だと思います。