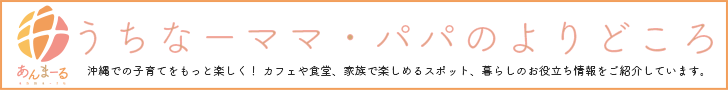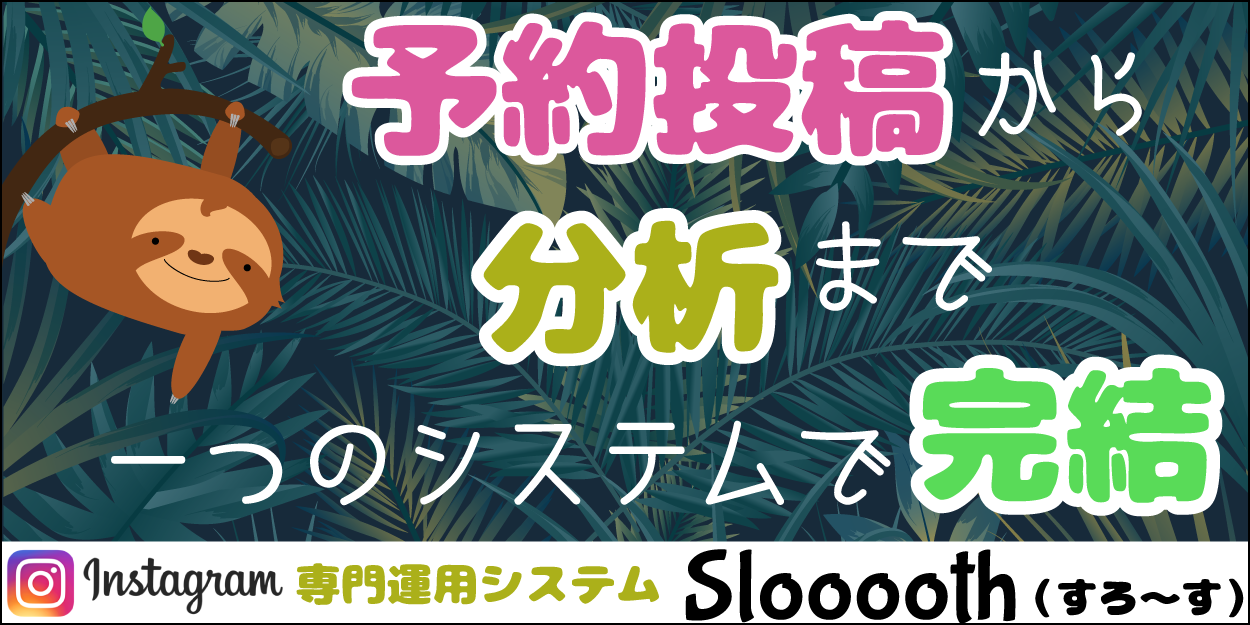複数アカウントで再確認することで大事故を回避できた実際の話
「インターネットサービスの利用方法を紹介する記事を書くなら、複数アカウントで確認したほうがいい」というお話をしようと思います。
インターネットサービスというのは、SNSであったり、広告であったり、その他のSaaSであったりとさまざまです。
特に、海外発のサービスを紹介する場合は要注意です。
今回は、私が実際にやらかした、時間をかけて完成させた解説記事がほぼ無駄になってしまった出来事について紹介します。
目次
どうやらテストケースに当たってしまったらしい
私がまるまる無駄にしてしまった解説記事は、ある広告サービスの利用手順を解説したものでした。
結論からいえば、これは確証があるわけではないのですが、どうやら私のアカウントがテストケースに当選してしまい、それに気づかないまま作成を進めてしまったということです。
一番しんどかったのが、スクリーンショットの見直しでした。
サービスの利用手順を解説する記事ですので、当然、ユーザーの理解の一助となるようにスクリーンショットを必要な箇所に入れます。
スクリーンショットの用意はとても大変です。撮るだけならボタン一発だけど、それを綺麗に切り抜き、クライアントのレギュレーションに合わせてリサイズし、メールアドレスなどが表示されていればボカシを入れ、誰の手に渡っても迷わないように画像に番号を振り、記事の正しい箇所に挿入する……
解説記事ともなればスクリーンショットの枚数は20枚、30枚、ときに50枚になることも。
それがほぼ無駄になってしまいました。
テストケースというのは、サービス内容の改変を行う前に、それが本当にいい改変なのかを小規模の環境でテストするものです。
WebマーケティングにおいてA/Bテストという言葉はよく知られていますが、大規模サービスのベンダーも当然テストを行います。
ただ、もちろん、それがテストケースであることはユーザーには通知されません。通知してしまうとテストにならないからです。
私はそのケースにおそらく当たってしまったわけですが、何が問題なのかを整理すると、テストケースをベースに解説記事を作ってしまうと「大部分のユーザーの画面とは違う話をしている」ことになってしまうんですね。
これでは解説記事になりません。
クライアントの利益を損なうだけでなく、エンドユーザーにも無意味な情報を伝えてしまうことになります。
スクリーンショットが特に大変だったと書きましたが、このテストではサービスの利用手順まで変わっていたので、そこも無駄になりました。
いったい何時間が虚空に消えてしまったのか……。
ライターゆえに「テスト」に気づきにくい
あまり好きな表現ではないのですが、いわゆる「コタツ記事」の作成を主な生業にしているライターの方々は、まったく専門ではないトピックの記事を書くことも多いはず。
もちろん、クライアントやエンドユーザーの利益のため、事前にできうる限りの下調べをし、その瞬間だけでも専門家として記事作成に当たっていることだと思います。
ただ、この場合の弱点として、例えばサービスの利用手順を解説する記事の場合、「変化」に気づきにくいということが挙げられます。
その瞬間だけ専門家になれても、一瞬前のことはわからないわけです。
とはいえこれがデメリットとなるケースはそうそう起きないものだと思っていたのですが、今回の私のケースがこれですね。
私はその広告サービスを常日頃から使っていたわけではないので、自分のアカウントがテストケースに選ばれたかどうかなんて知るよしもなかったのです。
なぜテストケースだと気づけたのか?
テストケースと気づかずに記事作成を最後まで進め、工数をまるまる水泡に帰してしまった私ですが、クライアントへの納品手前でギリギリ気づくことができました。
本当に危なかった。
これは、記事完成後、「一応他のメディアの記事も見ておくか」と念のため確認したために回避できたのでした。
もちろん着手前に他のメディアの記事はチェックしていましたが、スクリーンショットをまじえて手順を紹介する記事なので、実際に自分でサービスを触りながらスクリーンショットを撮っていくほうが確実です。
なので、他メディアを入念に見ていたわけではありませんでした。
最後に念のため再確認してみると、他メディアに掲載されているスクリーンショットは画面が全然違う。
これはおかしい……と。
本記事ではテストケースに当たってしまったと紹介していますが、本当にテストかどうか100%の確証はありません。なんせテストなので、どこにも通知がないのです。
ただ、「自分のスクリーンショットと他メディアのスクリーンショットが違う」理由がわからないと、クライアントに説明しようがありません。
なので、私は調べまくりました。
調べまくった結果、自分と同じ画面を掲載しているメディアは観測した限りではありませんでした。
そしてここで、冒頭の「インターネットサービスの利用方法を紹介する記事を書くなら、複数アカウントで確認したほうがいい」に帰ってくるのですが、別アカウントでも確認してみたのです。
そうすると、他メディアのスクリーンショットと同じ画面が出るではないですか。
なるほど、これはテストケースに当たってしまったんだな……と、一応の理由を見つけることができました。
なお、作成にかかった工数が無駄になっただけでなく、このからくりを解くためにもかなりの時間を要しました。
悪魔の証明に近い作業なので、泣きそうでしたね。
インターネットサービスは突然変わる
というわけで、「インターネットサービスの利用方法を紹介する記事を書くなら、複数アカウントで確認したほうがいい」という話でした。
なかなかないケースだとは思いますが、このタイミングでテストケースに当たってしまうと悲惨です。
また、テストではなくても、新機能のリリース時に一部のアカウントから順次開放していくということは十分にあります。
複数アカウントで見ておくと、変化がわりと多いインターネットサービスの「前後」について気づけることもあるでしょう。
なお、今回は私に実際に起きたケースを紹介しましたが、ここまで書いておいてなんですが、複数アカウントで確認はけっこう手間で現実的ではないと思います。
今回のケースから得られる教訓は「できる確認はできるだけやっておくのがいい」ですね。
どんなライティング、どんな仕事にも、想定外の落とし穴はあります。
「これはまぁいいか」とスルーせずに丁寧に物事を進めることで、少なくとも大事故は回避できるはずですね。