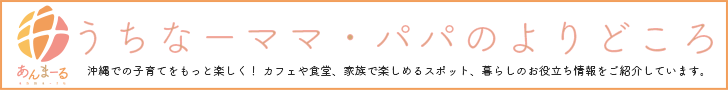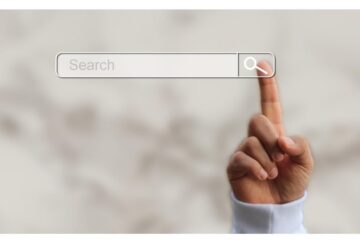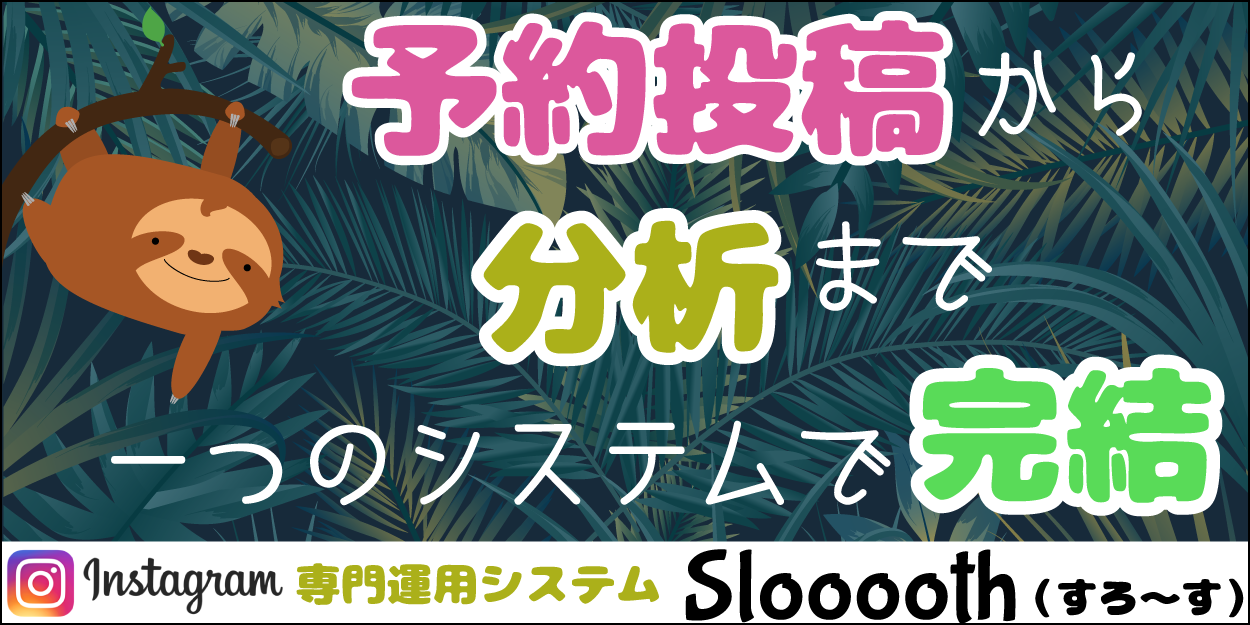記事の作成・更新において常に立ち返りたい「クエリ理解」について
「このキーワードでどうやって書けばいいんだ…?」と思うことは、わりと少なくありません。ライターのみなさんの中にも、同じ経験をしたことがある方は多いのではないかと思っています。
SEOを目的とした記事を作成・更新する際、キーワードは重要です。キーワードはそもそもトピックですし、タイトルや見出しに入れたいし、対策キーワードにおける検索順位の上昇が大きな目標となります。
でもこのキーワードではライティングが難しい……そう思ったとき、私は「クエリ(キーワード)の理解」という原点に立ち返ります。たいていの場合、クエリ理解を深めようとすると、ライティングの幅が広がっていい記事が書けるようになります。
今回は、私が普段から実践しているクエリ理解についてまとめます。
目次
そもそも「クエリ」ってなんだ?
実践内容についてまとめる前に、用語の意味から整理しておきましょう。
「クエリ」は英語で「疑問」「質問」を意味する言葉ですが、SEOにおいては「ユーザーが検索窓に入れる単語・フレーズ」を意味します。
SEOの施策においてより頻出する「キーワード」と同じ意味に聞こえますが、キーワードはWebサイト運営側(クライアント・制作会社・ライターまで含む)から見た施策のための言葉で、クエリはユーザーから見た検索単語・フレーズを指すという違いがあります。
記事の作成・更新、ひいてはSEOの施策においては、「クエリ理解」が重要となります。
なお私の中では、「クエリ理解」と「キーワード理解」はけっこう別物です。これについては本記事の後半で解説しようと思います。
「クエリ」の意味を理解するのに役立つ4つの分類
その単語の意味を理解するにあたって、分類を知ることはかなり有効です。
「クエリの辞書的な意味はわかったけど、実際のところどういうこと?」という疑問が残る場合は、クエリを4つに分類してみると理解しやすくなるかなと思います。
よく言われている4つの分類は、以下のとおりです。
・Goクエリ
・Doクエリ
・Buyクエリ
・Knowクエリ
Goクエリ
Goクエリとは、物理的にどこかへ行きたい場合はもちろん、特定のWebサイトを訪問したい場合などにも該当するクエリです。ユーザーは具体的にどこへ行きたいかが定まっている状態であり、欲しい答えが決まっています。多くの場合は固有名詞を含み、その場合は指名検索となります。
「北海道 行き方」
「マイクロソフト サポート」など
Doクエリ
Doクエリは、何かをやりたいと思っているときに検索に入れるクエリです。ユーザーは何をしたいのかがはっきりした状態であり、欲しい答えは決まっていますが、それを達成するために何を選択するのかは決まっていません。
「水道 修理」
「中古車 売却」
「インスタグラム ビジネスアカウント」など
Buyクエリ
GoクエリやDoクエリのうち、購入の意図をふくむクエリをBuyクエリと呼びます。
固有名詞を含む場合は買いたいものがほとんど決まっていますが、含まない場合はまだ検討状態といえます。
「iPhone 口コミ」
「プレゼント 女性 同僚」
「CRM おすすめ」など
Knowクエリ
何かしらの知識を得たい、解決策を知りたいといった場合に検索に入れるクエリをKnowクエリといいます。
ユーザーは期待する答えが定まっている場合もあれば、何がゴールかもわかっていない場合もあります。
「日本で一番長い川」
「名刺交換 順番」など
ライティングの深みを増すための「クエリ理解」
前置きが長くなりましたが、ここから私が実践しているクエリ理解についてご紹介します。
「Googleアナリティクス 分析方法」はどのクエリ?
実務において、対策キーワードを4つのクエリに分類することはほとんどありませんが、ここでは例として「Googleアナリティクス 分析方法」のクエリを4つの種類のどれかに分類してみます。
一見すると、Googleアナリティクスの分析方法を知りたいということで、Knowクエリです。
ただ、これだとクエリ理解は足りません。
「Googleアナリティクス 分析方法」で検索したユーザーは、分析方法を知れたらそれでいいのではなく、その先に「レポートを作成したい」「クライアントに提出しなければならない」という目的があります。
ユーザーには成し遂げたいことがあるので、これはDoクエリに分類されます。
記事を掲載するメディアや案件によってターゲット(ペルソナ)は違うので、これが正解という書き方はありませんが、Googleアナリティクスの分析方法を丁寧に紹介するだけでは不十分なことは間違いありません。
例えばレポートの出力方法までを解説したり、分析内容から改善策を立てる例を紹介したり、といった書き方があるでしょう。
「Instagram 広告 出し方」はどう理解する?
Webマーケティング関連のメディアでは、わりとありがちな対策キーワード「Instagram 広告 出し方」について理解してみます。
クエリの理解から記事ライティングの内容に落とし込む際、少し複雑なのは掲載メディア・案件のターゲット(ペルソナ)にも合わせなければならない点です。
ただし、これも合わせることでよりクエリ理解は深まります。
わかりやすくターゲットを切り分けると、メディアによって「Instagram広告出稿の実務を任された担当者」がターゲットの場合、「Instagram運用を一手に担っているマーケター」がターゲットの場合、が考えられます。
ここでは、前者を想定してみます。
「広告出稿の実務を任された担当者」が「Instagram 広告 出し方」で検索する場合、Meta広告マネージャの使い方についてまず調べたいと考えているはずです。
一方、そもそもInstagram広告についてあまりわかっていないだろうと想定できるので、単純な使い方に留まらず、広告の効果やクリエイティブのポイントなどについても解説の余地があるでしょう。
この場合、記事内であまり詳しく解説したくないのは「費用」面です。実務の担当者は費用面についてはノータッチだと想定できるため、「自身にとって必要ない情報」だと判断され、エンゲージメントが下がる可能性があります。
一方、費用について知りたい人がこの記事にたどり着いたケースを考えて、費用についてしっかり解説した別記事へ内部リンクを張るといいかもしれません。
「Instagram 広告 出し方」で方法を知った先には、「上司にパフォーマンスを求められている」という背景や「効率的に運用したい」という目的があるはずです。
そのため、単純な解説記事に終始するのではなく、広告運用のパフォーマンスを高めるTipsもあればターゲットの課題解決につながると期待できるでしょう。
このようにクエリを理解することで、ライティングの幅は広がり、記事の深みが増すことになります。
クエリを理解した記事はターゲットの課題解決につながり、エンゲージメントが上がり、SEOにおける評価が高まって、うまくいけばコンバージョン率の向上にもつながるかもしれません。
クエリ理解とは似て非なる「キーワード理解」
クエリとキーワードは実際のところ同じもの(検索窓に入力される単語・フレーズ)を指すものの、私の中では、「クエリ理解」と「キーワード理解」はけっこう違います。
実際の例として、私が新人ライターの仕事をチェックしているときに、「地下鉄 広告」というフレーズで対策をしたことがありました。
ある程度経験を積んだライターのみなさんであれば、案件やクライアントの情報を見ずとも、これが「地下鉄に広告を出稿してみたい事業者」向けの記事であることはわかるかと思います。
しかしこのときの新人ライターは、「地下鉄に掲示されている広告とはどんなものか」という、乗車客に説明するような内容で進めようとしていました。
けっこう極端な例だとは思いますが、こういう「そもそもキーワードが指している内容を理解しないまま進めてしまう」ということは起こり得ますし、私自身、あとから「これはキーワード理解が違ったかもしれない」と思い直すことがあります。
また、これは上記とも違ったタイプの例ではありますが、こんなこともありました。
対策するキーワードではなかったのですが、「機械可読目録」という言葉があります。多くの人には聞き慣れない言葉かもしれません。
ご存じでない方はぜひ検索して調べてみてほしいのですが、検索結果上位から答えを知ることができるものの、少し調べ進めてみるとおかしな記述が増えてきて混乱します。
「機械可読目録」は、ある業界において、どこから変わってしまったか、驚くほど間違った意味として捉えられ、少なくないメディアで誤情報が拡散されているのです。
私が関わった案件では、私がどうにか気づけたので誤情報を広めることはなかったのですが、実際に今でも誤情報が掲載されたままGoogle検索結果の1ページ目に表示されています。
これはシンプルに、言葉の意味をきちんと理解しないまま進めてしまったケース。
これは対策キーワードにおいても起こり得る問題で、クエリ理解とはまた別物であることがわかります。
こういったことから、私の中で「キーワード理解」は「クエリ理解」より前段階にあるものとなっています。
まとめ
記事の作成・更新を行うとき、私はキーワード理解とクエリ理解を別段階のものとして捉えています。
まずはキーワード理解。ライターとして多少はスキルがついていると思っていても、これを怠るとうっかり酷いことになります。
次に、ターゲット(ペルソナ)はどういう状況でその検索を行い、どんな結果を求めているのかを想像するクエリ理解です。
クエリ理解をしっかり行えば、記事の作成・更新において、何を書けばいいのか迷うことはかなり少なくなります。